三菱商事の洋上風力発電撤退で問われる日本のエネルギー戦略とは?洋上風力発電プロジェクト撤退の衝撃。コスト増と政策への影響。
日本の洋上風力発電に激震!三菱商事、秋田・千葉沖の大型プロジェクトから撤退。コロナ禍、ウクライナ危機、コスト増…再生エネ転換の遅れ、地域経済への影響も。低入札価格の落とし穴、FIP制度の課題、そして再エネ戦略の再考を迫る。撤退事例から学び、持続可能な洋上風力事業のあり方を模索する。
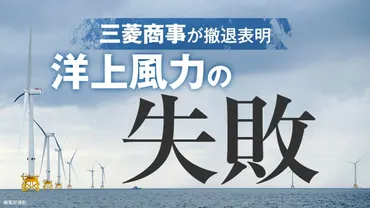
💡 三菱商事による洋上風力発電プロジェクトからの撤退が決定。建設コストの高騰が主な要因。
💡 撤退は、日本の再生可能エネルギー政策、特に洋上風力発電の将来に影を落とす結果となった。
💡 撤退の背景には、インフレ、円安、そして入札時の安値落札という複合的な要因が絡み合っている。
それでは、再生可能エネルギーへの転換を目指す日本において、大きな影響を与えることとなった三菱商事の洋上風力発電事業撤退について、詳しく見ていきましょう。
衝撃の撤退発表:再生可能エネルギーへの道に影を落とす
三菱商事撤退、洋上風力発電への影響は?日本の未来は?
再生エネ目標に遅れ。地域経済への悪影響も。
三菱商事の洋上風力発電プロジェクトからの撤退は、日本のエネルギー政策にとって大きな衝撃となりました。
再生可能エネルギーへの転換を目指す日本にとって、洋上風力発電は重要な要素の一つです。
公開日:2025/09/18
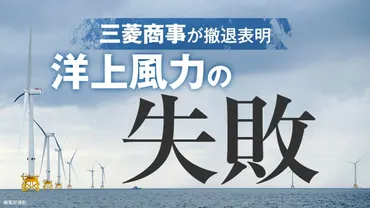
✅ 三菱商事を中心とする企業連合が、秋田県沖と千葉県沖の洋上風力発電プロジェクトから撤退を決定した。
✅ 撤退の理由は、インフレや円安による建設コストの増加で、応札時と比べて2倍超に膨らんだため。
✅ 地元関係者からは困惑や落胆の声が上がったものの、協議は淡々と進んだ。
さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/904027三菱商事の撤退は、再生可能エネルギーへの移行を目指す日本のエネルギー政策に大きな影響を与える可能性があります。
洋上風力発電の重要性に改めて気づかされました。
三菱商事による秋田県沖と千葉県銚子市沖での洋上風力発電事業からの撤退は、日本のエネルギー政策に大きな衝撃を与えました。
2021年の入札で落札した3つのプロジェクト(合計170万kW)は、再生可能エネルギーへの転換を目指す日本にとって、洋上風力発電の重要な一翼を担うはずでした。
しかし、新型コロナウイルス感染症の蔓延、ウクライナ危機、インフレ、為替変動、金利上昇といった外部環境の悪化により、事業継続が困難と判断されました。
この決断は、2040年の再生可能エネルギー比率目標達成への遅れ、特に洋上風力発電への期待の大きさ、そして地域経済への影響を強く懸念させるものでした。
なるほど、これは大きな問題ですね。ミリオネアとしては、投資判断の難しさを改めて感じますね。入札価格の決定は、企業経営の根幹を揺るがす問題にもなり得るわけです。
撤退の背景:安値落札と事業環境の悪化
三菱商事撤退が浮き彫りにした日本のエネルギー政策の課題は?
コスト増吸収の失敗と脱炭素化の遅れです。
三菱商事の撤退の背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。
入札時の価格設定、その後のコスト増加、そして政策的な課題など、多角的に分析してみましょう。

✅ 再エネと環境価値を自社施設で同時に利用するPRに関する記事です。
✅ 記事の具体的な内容は不明ですが、自社施設での再エネ利用を促進するような内容だと推測されます。
✅ 環境価値の循環に焦点を当てていることから、環境負荷低減への取り組みをアピールする意図があると推測されます。
さらに読む ⇒環境ビジネスオンライン トップページ出典/画像元: https://www.kankyo-business.jp/news/4201d1e4-b081-4739-b683-2f54c1083f49三菱商事の撤退は、企業経営とエネルギー政策の両方に課題を突きつけました。
入札価格、コスト増、そして政府の支援策など、様々な要素が絡み合っているようです。
三菱商事の撤退は、単なる企業の判断に留まらず、日本のエネルギー政策が抱える課題を浮き彫りにしました。
撤退の主な要因は、入札時に提示した低い供給価格が、その後のコスト増を吸収できなかったこと、さらには、風車メーカーの変更や工法の見直しといった対策も功を奏さなかったことにあります。
三菱商事は、2025年3月期決算で524億円の減損を計上し、撤退に伴う追加損失は限定的としていますが、共同事業者であるシーテックは170億円程度の損失を見込むことになりました。
また、政府のエネルギー基本計画において、洋上風力発電は重要な役割を担っていましたが、今回の撤退は、発電開始時期の遅延を招き、脱炭素化の目標達成に遅れが生じる可能性を高めました。
撤退案件以降、入札方式はFIP(フィード・イン・プレミアム)へと変更されましたが、FIP案件においても、PPA(電力購入契約)による売電単価確保が重要となっています。
確かに、競争入札ってのは、良い面もあるけどリスキーよね。コストをどこまで見込めるか、ってのが難しいところだわ。政府も、もっと長期的な視点での政策が必要なんじゃないかしら。
次のページを読む ⇒
三菱商事、洋上風力3プロジェクトから撤退。低価格入札の裏でコスト増。再エネへの影響、今後の事業戦略とは?

