飲食業界の倒産ラッシュと生き残り戦略:コロナ禍、テイクアウト、変化への対応とは?飲食業界の現状分析:倒産増加の原因と、生き残りをかけた変化への対応
コロナ禍で激変した飲食業界。倒産件数増加、物価高騰、人手不足…厳しい現実を乗り越えるには、デリバリー、テイクアウト、オンライン販売など「家で楽しめる」戦略への転換が必須。SNS活用、コスト削減、人材確保、訪日外国人へのアプローチもカギ。中小店舗が生き残るための多角的な戦略と、変化に対応する持続可能な経営が求められる。

💡 2023年の飲食業倒産件数は過去最多を更新、コロナ禍と物価高騰が原因。
💡 テイクアウト、デリバリー、新たな価値創造が生き残りの鍵となる。
💡 変化する消費者行動に対応し、未来を見据えた戦略が必要不可欠。
まず、飲食業界を取り巻く現状と、飲食業界が抱える問題点について見ていきましょう。
コロナ禍と飲食業界の試練:倒産増加と現状分析
飲食業界の倒産増加、その原因と2024年の更なる課題は?
顧客認知、物価高騰、人手不足など複合的な要因。
飲食業界は、コロナ禍からの影響で厳しい状況にあります。
倒産件数は増加し、人手不足や物価高騰も追い打ちをかけています。

✅ 2023年の飲食業倒産は893件と過去最多を更新し、前年比71.0%増となった。これはコロナ禍の支援策終了、人手不足、物価高騰による収益圧迫が主な原因。
✅ 倒産の増加は、特に専門料理店、居酒屋、宅配飲食サービス業で顕著。原因別では販売不振が最多で、その多くが新型コロナ関連倒産であり、コロナ禍の影響が長期化していることが示唆されている。
✅ 人件費、食材費、光熱費の高騰、人手不足、価格転嫁による客足減少など、収益を圧迫する要因が複合的に影響し、今後も幅広い業態で倒産が増加する可能性がある。
さらに読む ⇒東京商工リサーチ出典/画像元: https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198274_1527.html倒産増加の原因は多岐にわたりますね。
コロナ禍の支援終了、人手不足、物価高騰と、複合的な要因が重なっていることがよく分かります。
2020年からのコロナ禍は、飲食業界に大きな打撃を与え、その影響は今も続いています。
外出自粛による客足の減少、固定費の負担増、そして2023年には過去最多を記録した倒産件数が、業界の厳しい現実を物語っています。
倒産の主な原因としては、顧客への認知不足、不明瞭なコンセプト、立地・物件選びの失敗、キャッシュフロー管理の甘さ、人材教育の軽視などが挙げられます。
2024年には、コロナ禍からの回復の遅れに加え、物価高騰、光熱費の上昇、人手不足といった複合的な要因が重なり、小規模店舗を中心に廃業が相次いでいます。
特に、物価高騰は食材費や光熱費を圧迫、人手不足は人件費を押し上げ、経営を困難にしています。
なるほど、コロナ禍で飲食業界は本当に大変だったんだな。でも、倒産した原因をしっかり分析して、次の対策に活かせるようにしないとな!
生き残りのための戦略:変化への対応と新たな価値創造
飲食店、生き残り戦略は?脱「店舗」で何が変わる?
デリバリー、テイクアウト等、「家で楽しめる」提供。
生き残りをかけた飲食店は、テイクアウトなど、新たな戦略を模索しています。
デリバリーやテイクアウト需要への対応が重要になってきます。
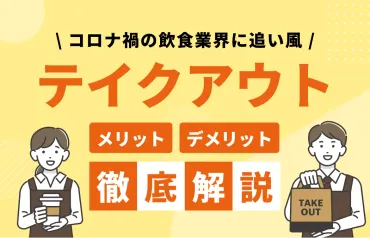
✅ テイクアウトとは、飲食店で注文した料理を店内で食べずに持ち帰ることで、多様な食事スタイルに対応し、店と顧客双方にメリットがある。
✅ 英語圏では「テイクアウト」ではなく、アメリカでは「to go」、イギリスでは「take away」が一般的であり、テイクアウトの反対語は「dine in」(アメリカ/カナダ)や「eat in」(イギリス)などと表現される。
✅ 「テイクアウト」は洋食店やファストフード店で使われることが多く、和食店などでは「持ち帰り」という言葉が使われる傾向がある。
さらに読む ⇒ビジネスの課題を解決し、利益UPにつながるITマッチングプラットフォーム|Wiz cloud(ワイズクラウド)出典/画像元: https://012cloud.jp/article/takeout-merit-demeritテイクアウトって、もはや当たり前になってきましたよね。
顧客ニーズに応えるために、色々な工夫がされているんだなと感じました。
生き残りをかけた飲食店は、従来の「店舗に来てもらう」ビジネスモデルからの脱却を図り、「店舗に来なくても付加価値を提供できる」戦略へと転換しています。
具体的には、デリバリーサービスやテイクアウト、宅飲み需要への対応、オンライン飲み会への食の提供など、「家で楽しめる」顧客ニーズに応えることが重要です。
プラットフォームの活用や、テイクアウト予約サービスの導入も有効な手段です。
さらに、コスト削減(省エネ設備の導入、食材の仕入れ見直し)、価格戦略の見直し(値上げだけでなく、テイクアウトやデリバリーの導入)、人手不足対策(待遇改善、業務効率化、外国人労働者の活用)、新たな収益源の開拓(メニュー開発、イベント開催、オンライン販売)など、多角的な戦略が求められます。
顧客ニーズの変化に対応し、ターゲット層の明確化、SNSを活用した情報発信、顧客との関係性構築も重要です。
ほんと、テイクアウトって便利だよね。でも、お店側も大変なんだろうなぁ。コスト削減とか、色々考えないといけないこといっぱいあるんでしょ?
次のページを読む ⇒
外食産業はコロナ禍を乗り越え回復傾向!若年層と訪日客がカギ。テイクアウト、デリバリーなど、多様な戦略で生き残りを図る中小店舗にも注目!

