『行動科学マネジメント』石田淳氏のメソッドとは? 組織と個人の行動変容を促す秘訣とは?誰でも再現できる行動を促す!組織と個人の行動変容
行動科学マネジメントの第一人者、石田淳氏が語る、誰でも「できる」を実現する組織変革術。従来のマネジメントを超える、行動に焦点を当てた革新的な手法を解説。MORSの法則やベイビーステップを活用し、抽象的な指示を具体的行動へと落とし込む方法を紹介。ハイパフォーマーの暗黙知を可視化し、組織全体のパフォーマンスを底上げする秘訣がここに。部下の自発性を引き出す『子どもを伸ばす技術』もビジネスに応用。5500社以上が導入したノウハウで、あなたの組織も変わる!
「普通」の社員の能力を引き出す教育方法
社員の能力UP、上司の秘策は?小学5年生にもわかる教育?
MORSの法則で具体指示!行動の教科書を作る!
3つ目は、「普通」の社員の能力を引き出す教育方法についてです。
人材不足が叫ばれる現代において、既存の人材を最大限に活用するための教育方法を解説します。
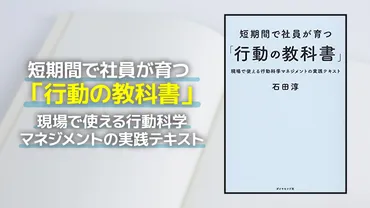
✅ 7割以上の企業が人手不足を感じており、優秀な人材を求めるのではなく、既存の人材活用に着手することが重要である。
✅ 人材育成のポイントとして、新入社員が求める「仕事をちゃんと教えてもらえる」環境を整えること、やってはいけない行動を具体的に示すこと、そして成功者の思考プロセスをフレームワークで共有し再現性を高めることが挙げられる。
✅ 下位8割の底上げこそが人材不足解決の鍵であり、指示待ちではなく自ら行動できる社員を育てるための具体的な方法が重要である。
さらに読む ⇒岡崎かつひろ ~Offical Web Site~|個人が輝く未来をつくる!出典/画像元: https://okazakikatsuhiro.com/article259/8割を占める「普通」の社員の能力を引き出すための具体的な教育方法ですね。
教科書のようなわかりやすい説明や、行動の教科書の7つのステップは参考になります。
本書は、大多数を占める「普通の社員」の能力を引き上げるために、上司が実践すべき教育方法を解説しています。
人材の割合が「できる人2割、普通の人6割、できない人2割」という法則に基づき、人手不足の現代において、全体のレベルアップを図る重要性を強調しています。
具体的には、8割を占める「普通以下の人」に対して、明確で具体的な行動を指示すること(MORSの法則:Measurable Observable Reliable Specific)が重要であると説いています。
教科書は、小学5年生でも理解できるレベルの言葉遣い、最小限のボリューム、具体的な行動指示がポイントです。
行動の教科書は、できる社員の行動観察、インタビュー、思考プロセスのフレームワーク化、ピンポイント行動の抽出、言語化、脚本化、結果に直結しない行動の原因特定と環境変化、望ましい行動の定着・習慣化という7つのステップで作成します。
これらの方法論を通じて、会社全体のパフォーマンス向上を目指します。
なるほどね! 優秀な人材を求めるだけじゃなくて、今のメンバーを育てるって大事よね。小学生でもわかるようにってのは、わかりやすくていいね!
子どもの教育とビジネスにおける行動変容の共通点
『子どもを伸ばす技術』、ビジネスにも活かせるって本当?
自己肯定感を育む接し方が、自発性を促します。
4つ目は、子どもの教育とビジネスにおける行動変容の共通点です。
子どもの成長と、ビジネスにおける人材育成は、実は共通点が多いのです。
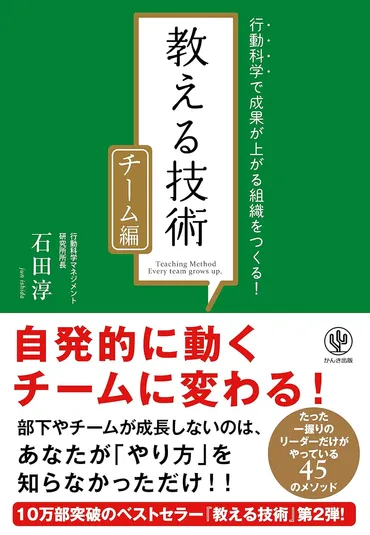
✅ 本書は、行動科学に基づいた「教え方」のノウハウをまとめたもので、リーダーや経営者向けに、短時間で「できない人」を「できる人」に変えるための具体的な方法を解説しています。
✅ 「ほめ方」「叱り方」といった基本的な指導方法に加え、リモートワークやハラスメント対応など、現代のビジネスシーンに対応した内容も含まれています。
✅ 著者の石田淳氏は、行動科学マネジメントの第一人者であり、1500社以上の企業や4万人以上のビジネスパーソンを指導した経験をもとに、実践的な人材育成メソッドを紹介しています。
さらに読む ⇒ かんき出版出典/画像元: https://kanki-pub.co.jp/pub/book/9784761277987/子どもを伸ばす技術が、部下を伸ばす技術にも繋がるという点が興味深いです。
親や上司がネガティブワードを控えることの重要性にも気づかされました。
石田淳氏が紹介している電子書籍『子どもを伸ばす技術』は、ビジネスパーソンにも役立つ内容を含んでいます。
この書籍は、子どもの自己肯定感を育み、自発的な行動を促す親の接し方を紹介しており、ビジネスにおける「指示待ち人間」を改善するヒントにもなります。
子どもの頃の否定的な言葉が行動を抑制することと、ビジネスの現場での否定的な環境が同様に自発性を阻害することを説明し、行動科学マネジメントの「ABCモデル」を用いて、人間の行動原理は子どもも大人も変わらないと論じています。
親や上司がネガティブワードを控え、自ら行動できる環境を整えることの重要性を強調し、『子どもを伸ばす技術』が「部下を伸ばす技術」にも繋がると述べています。
んー、まるで子育てと一緒だね! 否定的な言葉は、子どもの可能性を摘んでしまうのと同じように、部下のモチベーションも下げちゃうってことか。
行動KPIと暗黙知の形式知化
成果を出す「ピンポイント行動」を可視化する秘訣は?
行動KPIで分析し、誰でも真似できるようにすること。
最後に、行動KPIと暗黙知の形式知化についてです。
組織全体のパフォーマンスを向上させるために、成果に繋がる行動をどのように可視化するのか、その方法を解説します。
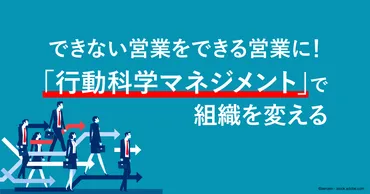
✅ 少子高齢化による労働人口減少を受け、多くの企業は人材の囲い込みに注力しているが、人材流動性の高まりから、一部のハイパフォーマーへの依存はリスクとなっている。
✅ 組織全体の底上げのためには、ハイパフォーマーの「結果に結びつく行動」を特定し、他の社員にその行動を定着させる「行動科学マネジメント」が有効である。
✅ 行動科学マネジメントは、人の内面ではなく「行動」に焦点を当て、再現性を重視することで、どんな個性や価値観の持ち主でも、同じような結果を得られるようにする手法である。
さらに読む ⇒SalesZine(セールスジン)出典/画像元: https://saleszine.jp/article/detail/4975ハイパフォーマーの行動を分析し、KPIとして可視化することは非常に重要ですね。
暗黙知を形式知化することで、組織全体のレベルアップに繋がると思います。
成果に繋がる行動、すなわち「ピンポイント行動」を特定し、それを増やすための「行動KPI」の重要性について解説します。
ハイパフォーマーのピンポイント行動は、彼ら自身では意識していない「暗黙知」であることが多く、単なるヒアリングだけでは特定が難しいと指摘しています。
ハイパフォーマーの行動を詳細に分析し、数値化することで、誰でも真似できる形で行動を可視化する必要があります。
石田淳氏のYouTubeチャンネル「行動科学マネジメントの視点」や、提供されている無料PDFレポートを通じて、5500社以上の企業で導入されてきた行動科学マネジメントのノウハウを学ぶことができます。
KPIの設定ってのは、まさにビジネス版の宝探しだね! 成功者の行動を真似すれば、誰でも成功に近づけるってことだべ?
本日は、石田淳氏の行動科学マネジメントについて、様々な角度から解説しました。
組織と個人の行動変容を促すための具体的な方法が理解できました。
💡 行動科学マネジメントは、再現性を重視し、具体的な行動指示と継続支援が重要です。
💡 MORSの法則やベイビーステップを活用することで、目標達成に向けた行動を促します。
💡 子どもの教育とビジネスにおける人材育成は共通点が多く、ポジティブな言葉が重要です。


