スガキコシステムズの未来への投資?:給与・休日改定で人材獲得競争に挑む?2026年4月入社 正社員初任給28万円! スガキコシステムズの改革
愛され続ける「スガキヤ」の秘密、教えます! スガキコシステムズが、人材獲得競争激化に対応!年間休日増、新卒給与UP! 伝統の味を守りつつ、新業態も展開。従業員の働きがいを高め、成長を加速させるための改革! 年収・評価制度も公開。未来への投資で、更なる「美味しい」と「楽しい」を届ける!
従業員の声:年収、評価制度、そして働きがい
年収400万円!社員の給与事情、満足度と課題は?
平均400万円、昇給も。不満は残業代と昇給幅。
昇給とは、職務上の昇格や勤続年数などに応じて賃金が上がること。
昇給を目指すには、資格取得やスキルアップが有効です。
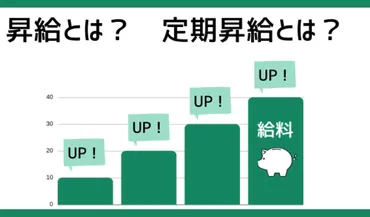
✅ 昇給とは、職務上の昇格や勤続年数などに応じて賃金が上がることです。定期昇給やベースアップなど、様々な種類があり、企業によって制度が異なります。
✅ 昇給を目指すには、資格取得やスキルアップが有効です。また、昇給の有無や制度について、入社前に確認することも重要です。
✅ 昇給と混同されやすい用語として、昇格や昇進があります。昇格は等級が上がること、昇進は役職が上がることです。
さらに読む ⇒転職はマイナビ転職-豊富な転職情報で支援する転職サイト出典/画像元: https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/103/従業員の声からは、昇給や評価基準に対する様々な意見が聞こえてきます。
評価基準の明確化や、昇給幅の改善は、今後の課題となるかもしれません。
従業員の年収に関する情報も存在します。
回答者52人の平均年収は400万円、年収範囲は220万円から615万円です。
職種別では、営業系388万円、企画・事務・管理系437万円、販売・サービス系398万円となっています。
年齢別に見ると、25~29歳が375万円、30~34歳が441万円です。
賞与が年2回支給され、残業代が正しく支給されること、評価基準を満たせば昇給があるといった給与制度があります。
しかし、管理職は残業代が出ないことや、仕事量に見合う給与が得られない、昇給幅が小さいといった不満の声も存在します。
評価は、社歴に関わらず顧客のために行動できる人が評価される傾向があり、半期に一度の上長からのフィードバックを通じて自己のスキルアップを図れるようです。
ふむふむ、年収は人それぞれね。でも、ちゃんと評価されて、頑張れば給料も上がるってのは良いことだね!
未来への展望:スガキコシステムズの更なる発展
スガキコ、年収と労働環境改革の目的は?
未来への投資、更なる「美味しい」と「楽しい」のため。
スガキコシステムズは、2026年4月より、人材獲得のため、年間休日を116日、大卒初任給を28万円に改定します。
店長やエリアマネジャーへのキャリアアップもサポート。

✅ スガキコシステムズは、2026年4月より、優秀な人材獲得のため、年間休日を116日(+8日)、大卒初任給を28万円(+5万円)に改定します。
✅ 今回の改定は、人材が安心して業務に集中できる環境整備と、努力と成果に応じた報酬配分を行い、若い世代の挑戦を支援し、店長やエリアマネジャーへのキャリアアップをサポートすることを目的としています。
✅ 伝統の味を守りながら、新業態への挑戦を続けるスガキコシステムズが、従業員の働きがいを高め、更なる成長を目指すための人材投資となります。
さらに読む ⇒Infoseekインフォシーク - 楽天が運営するニュースサイト出典/画像元: https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000047_000097460/人材への投資は、企業の成長に不可欠です。
従業員の働きがいを高め、未来への投資を続けるスガキコシステムズの姿勢は素晴らしいですね。
スガキコシステムズ株式会社は、従業員と共に成長し続け、伝統の味を守りながら、お客様に最高の体験を提供することを目指しています。
人材育成と労働環境の改善を通じて、従業員一人ひとりの働きがいを高め、新しいアイデアやサービスが生まれる好循環を創出し、更なる成長を目指しています。
今回の年収と労働環境の改革は、未来への投資であり、スガキコシステムズが今後も「美味しい」と「楽しい」を提供し続けるための重要な基盤となるでしょう。
まさに!人材こそが最大の資産!従業員を大切にする会社は、必ず成功する!
本日の記事では、スガキコシステムズの給与・休日改定についてご紹介しました。
従業員にとって魅力的な条件ですね。
今後の発展に期待しましょう。
💡 スガキコシステムズは、2026年4月より、大卒初任給28万円、年間休日116日に改定します。
💡 従業員の働きがいを向上させ、人材獲得競争を勝ち抜くための施策です。
💡 伝統の味を守りながら、新しい食の可能性を追求し、更なる成長を目指します。


