LegalOn Technologiesが組織変革に挑む!哲学対話、360度フィードバック、思考力を磨くとは?組織変革の鍵は「哲学思考」!LegalOn Technologiesの挑戦
LegalOnTechnologiesが開催したワークショップでは、東京大学の堀越氏を招き、自己理解を深めるための「哲学対話」を実施。変化の激しい現代において、AppleやGoogleも採用するこの手法は、単なる意見交換ではなく、多様な考えを共有し、本質を問い、自律的に思考する力を育みます。360度フィードバックを基に、社員が自己を深く見つめ、組織変革を促進。哲学思考は、イノベーションと未来の組織を創造する可能性を秘めている。
「哲学思考」がもたらすビジネスへの変革
組織変革の鍵は? 斬新なイノベーションを生む思考とは?
哲学思考。本質を問い、自律的に探求する力。
現代のビジネス環境において、「哲学思考」が組織変革の重要な手段として注目されています。
本章では、その具体的な内容と、ビジネスへの応用について掘り下げていきます。
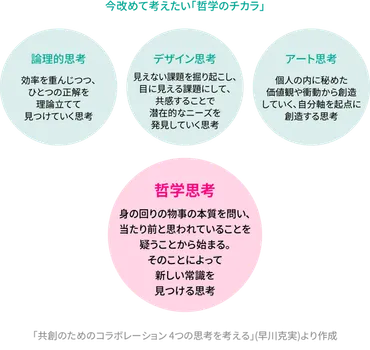
✅ 現代のビジネス環境における組織運営の課題に対し、「哲学思考」が注目されており、特に欧米では「哲学コンサルティング」が広がり、企業内哲学者も活躍している。
✅ 企業改革を阻む要因として、組織文化や個人の意識、変革への熱量の低さが挙げられており、自律的に問いを立て、探求する力を育成することが重要とされている。
✅ 「哲学思考」は「哲学的に考える方法」をビジネスに応用し、組織や個人に「自ら問いを立てて探求する態度」を根付かせ、ビジネスに変革をもたらす可能性を秘めている。
さらに読む ⇒ビジネス課題を解決する情報ポータル[ドゥ・ソリューションズ]出典/画像元: https://www.d-sol.jp/blog/philosophical-dialogue-for-business哲学思考が、組織変革の有力な手段として注目されているというのは、大変興味深いですね。
リスク回避傾向や自己啓発不足といった課題に対して、有効な解決策となり得るかもしれません。
現代のビジネス環境では、組織変革が喫緊の課題となっています。
そんな中、東京大学の堀越氏と電通の中町氏によるウェビナーでは、「哲学思考」が組織変革の有力な手段として注目されていることが語られました。
変革を阻む要因として、リスク回避傾向や自己啓発の不足といった課題が挙げられます。
この課題を克服するために、本質を問い、当たり前を疑う力、つまり「自律的に問いを立て、探求する力」の育成が不可欠であり、そのためのアプローチとして「哲学思考」が有効であるという問題意識が示されました。
「哲学思考」は、哲学的な思考、対話術、言語化能力を向上させ、イノベーションを促進することを目指します。
欧米では「哲学コンサルティング」や「企業内哲学者」の活躍が見られ、その効果が実証されています。
哲学思考って、なんだか難しそうだけど、組織を変える力があるなら、うちの会社でも取り入れてみたいわね。みんなで問いを立て、本質を見抜く力を育てて、もっと会社の業績を上げたいものだわ!
企業における哲学対話の効果と導入のヒント
企業哲学対話、成功の鍵は?安全・安心な環境?
安全・安心な場、マウンティング禁止、問い重視。
本章では、ウェブ電通報の記事を参考に、哲学対話が組織にもたらす効果と、導入のヒントについて解説します。
事例を通して、その具体的な効果を見ていきましょう。
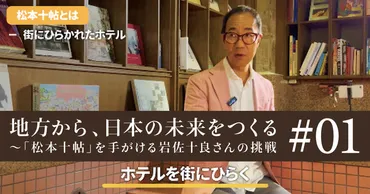
✅ ウェブ電通報の注目記事として、哲学対話が組織にもたらす効果、コロナ禍にオープンした宿の運営、リテールメディアの解説などが紹介されている。
✅ 東京大学の梶谷氏へのインタビューを通し、ビジネスの場で注目される哲学対話の効果や『きちんと話をする』経験の重要性について言及している。
✅ その他、宿の運営、リテールメディア、セイコーミュージアムなど、多様なテーマに関する記事が掲載され、ビジネスパーソンに新しい価値の発見と学びを提供している。
さらに読む ⇒プレスリリース配信サービス | 共同通信PRワイヤー出典/画像元: https://kyodonewsprwire.jp/release/202301162146哲学対話が、組織風土改革やコミュニケーション能力の向上に貢献する可能性があるというのは、素晴らしいですね。
安全な環境で、多様な価値観を尊重する土壌を育むことが重要とのこと、とても参考になります。
電通の中町氏がUTCPセンター長の梶谷氏にインタビューした内容によれば、企業における哲学対話は、組織風土改革や社員のコミュニケーション能力向上に貢献する可能性があります。
梶谷氏は、学校と企業でのテーマ設定の違いに言及し、仕事に関連するテーマは意見の多様性を阻害する可能性があると指摘しました。
まずは些細なテーマで「きちんと話をする」経験を積むことが重要です。
哲学対話は、組織内の固定観念を打破し、多様な価値観を尊重する土壌を育むことを目指します。
うまくいっている哲学対話の条件として、安全・安心であること、マウンティング行為がないこと、答えよりも新たな問いを生み出すことに重点が置かれていること、話した量より考えた質を重視することが挙げられます。
哲学対話の効果、素晴らしい!組織風土改革に繋がり、社員のコミュニケーション能力も向上となれば、まさに一石二鳥!企業は、もっとこういう取り組みに積極的に投資すべきだよ。将来の企業経営は、哲学思考が必須になるかもしれないな。
哲学対話の可能性:未来の組織文化を創造する
哲学対話、導入で何が変わる?企業の未来をどう変える?
思考力向上、チームワーク強化、イノベーション加速!
Googleの研究「プロジェクトアリストテレス」から得られた知見と、哲学対話の関連性について考察します。
未来の組織文化を創造するためのヒントを探ります。
公開日:2025/07/01
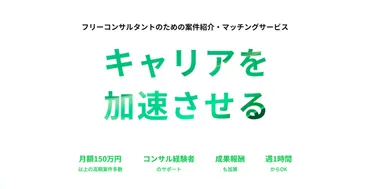
✅ プロジェクトアリストテレスは、Googleが実施した、成果を上げるチームの共通点を明らかにするための研究であり、約180チーム、数千人規模のデータを分析しました。
✅ この研究は、チームの成果に差が出る理由を「人」ではなく「チーム構造」から解明することを目指し、心理的安全性、信頼性、構造と明確さ、仕事の意味、仕事のインパクトという5つの特徴が重要な要素として見出されました。
✅ プロジェクトの名前は、古代ギリシアの哲学者アリストテレスの「全体は部分の総和以上である」という言葉に由来しており、チームという集合体の本質に迫るという意味が込められています。
さらに読む ⇒【月300万円】フリーコンサル案件紹介ならRe:neW|新規事業案件多数出典/画像元: https://re-new-vanes.com/magazine/project-aristotle/Googleのプロジェクトアリストテレスの研究結果と、哲学対話の特性が合致するというのは、非常に興味深いですね。
未来の組織文化を創造する上で、重要な示唆を与えてくれます。
哲学対話は、思考力向上、概念・理念の共有化、チームビルディングの強化といったメリットをもたらします。
企業への導入例として、「イノベーションの加速」や「法人営業」といったテーマが提示され、社員の思考力向上、組織内の情報共有、チームワークの強化に繋がることが期待されています。
Googleの「アリストテレス計画」で得られた効果的なチームの条件と、哲学対話の特性が合致すると考えられており、職場での哲学対話の導入は、組織文化を変革し、未来の組織を創造する可能性を秘めています。
Googleの研究って、すっごいな! チームの成果は、人じゃなくてチームの構造で決まるってのは、目からウロコだわ!哲学対話を取り入れて、うちのチームも最強にしなくちゃ!
LegalOn Technologiesの哲学対話導入事例は、組織変革のヒントに満ちています。
自己理解を深め、多角的な視点を得ることで、未来の組織文化を創造する可能性を感じました。
💡 LegalOn Technologiesは、哲学対話と360度フィードバックを組み合わせ、組織変革を推進。
💡 哲学対話は、自己理解を深め、多角的な視点を得るための有効な手段。
💡 哲学思考は、ビジネスにおける課題解決とイノベーションを促進する可能性を秘めている。


