LegalOn Technologiesが組織変革に挑む!哲学対話、360度フィードバック、思考力を磨くとは?組織変革の鍵は「哲学思考」!LegalOn Technologiesの挑戦
LegalOnTechnologiesが開催したワークショップでは、東京大学の堀越氏を招き、自己理解を深めるための「哲学対話」を実施。変化の激しい現代において、AppleやGoogleも採用するこの手法は、単なる意見交換ではなく、多様な考えを共有し、本質を問い、自律的に思考する力を育みます。360度フィードバックを基に、社員が自己を深く見つめ、組織変革を促進。哲学思考は、イノベーションと未来の組織を創造する可能性を秘めている。
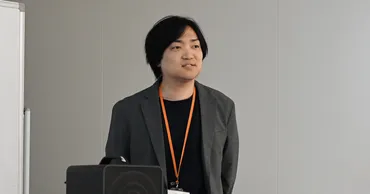
💡 LegalOn Technologiesが360度フィードバックの結果を基に、哲学対話ワークショップを実施し、自己認識を深めた。
💡 哲学対話は、答えのない問いを通して自己の体験を語り合い、多角的な視点を得ることを目指す手法。
💡 哲学思考は、ビジネスにおける組織変革の可能性を秘めており、イノベーションを促進する。
LegalOn Technologiesが組織文化改革の一環として導入した、哲学対話についてご紹介します。
この取り組みから得られる組織への変化、そしてその可能性について掘り下げていきましょう。
組織変革への第一歩:哲学思考との出会い
自己理解を深める秘訣?哲学対話、その効果とは?
多様な考えを共有し、理解を深める手法。
LegalOn Technologiesが組織変革の一環として、360度フィードバックの結果を踏まえ、哲学対話ワークショップを実施しました。
東京大学の堀越先生を迎え、組織の課題解決に挑みました。
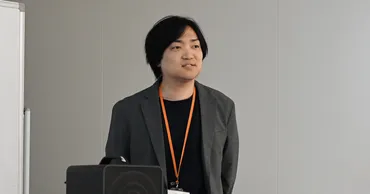
✅ LegalOn Technologiesは、360度フィードバックの深い理解のために「哲学対話」ワークショップを実施し、東京大学の専門家 堀越氏を招いた。
✅ ワークショップでは、360度フィードバックの結果を基に「考えの受け止め」などをテーマに設定し、参加者は答えのない問いについて自らの体験を語り、対話を通して「なんとなく」の理解を深めた。
✅ 「哲学対話」では、対話のルールやアプローチのコツを学び、「わかる」と「わからない」を同時に増やしていくことを目指し、自己認識を深め、多角的な視点を得ることを目的とした。
さらに読む ⇒LegalOn Now出典/画像元: https://now.legalontech.jp/n/n242cfbfca6b8LegalOn Technologiesの試みは、自己理解、多角的な視点を得ることを目的とした、素晴らしい取り組みですね。
360度フィードバックを活かしたワークショップ、大変興味深いです。
LegalOnTechnologiesが行った360度フィードバックからの深い気づきを得るためのワークショップでは、東京大学の堀越氏を招き、「哲学対話」という手法が採用されました。
堀越氏は、変化の激しいスタートアップ環境において自己理解を深めることを目指し、その重要性を強調しました。
哲学対話とは、答えのない問いについて参加者が車座になり、自らの体験を基に語り合うことで考えを深める手法です。
AppleやGoogleをはじめとする欧米の企業でも積極的に取り入れられています。
この手法は、単なる情報交換や意見交換ではなく、多様な考えを共有し理解を深めることを目指します。
なるほど、360度フィードバックを活かして、自己理解を深めるというのは、非常に有効なアプローチですね!スタートアップのような変化の激しい環境では、自己認識は成功への重要な鍵となるでしょう。堀越先生の指導も素晴らしい!
哲学対話の基本とワークショップ体験
哲学対話のキモは何?深める6つのコツとは?
自己の考えを深める場。6つのコツで対話を深めます。
哲学対話は、単なる会話ではなく、自己の思考を深めるための場です。
本章では、哲学対話の基本と、ワークショップでの具体的な体験に焦点を当てて解説します。

✅ 企業における哲学対話は、仕事への責任感からテーマが「会社」や「仕事」に偏りがちだが、本来は些細なテーマで「きちんと話をする」経験を積むことが重要。
✅ 哲学対話は結論を急がず、「話を聞くこと」「話すこと」自体を楽しむことを目指しており、それは全ての話し合いの基礎となる。
✅ 組織内での役割に基づいた会話ではなく、1人の人間として話すことで、新たな発見や解放感を得ることができる。
さらに読む ⇒ウェブ電通報/ビジネスにもっとアイデアを。出典/画像元: https://dentsu-ho.com/articles/8439哲学対話は、結論を急がず、対話そのものを楽しむことが重要というのは、とても納得できます。
組織内での人間関係を円滑にする上でも、非常に効果的な手法ですね。
ワークショップでは、まず哲学対話の基本的なルールが提示されました。
それは、対話は会話や議論ではなく、自己の考えを深める場であること、そして「いい人」であろうとする必要はない、というものです。
対話を深めるための6つのコツ(本質を問う、関係を問う、一般化に慎重になる、前提・理由を問う、思考実験する、例や反例を挙げる)も共有されました。
参加者は、事前に過去の360度フィードバックの結果を見返し、気になった点を書き出すという宿題に取り組んでいました。
堀越氏は、哲学対話は「わかりの経験」であり、『わかる』『わからない』を同時に増やしていくことだと説明しました。
社員たちは自己紹介を兼ねて、事前課題で得た内省ポイントを発表し、テーマについて議論を深めました。
ビジネスシーンで直面するテーマ(考えの受け止め、自分起点、自己変革など)について対話を通して理解を深めました。
うーん、哲学対話って、なんだか新鮮でワクワクするね!会社の役割とか関係なしに、一人の人間として話すってのが、いいんじゃない?わっちは、北海道弁で参加したいなぁ!
次のページを読む ⇒
組織変革のカギは「哲学思考」!東大×電通ウェビナーで議論された、本質を問い、イノベーションを促す思考法とは? 組織の未来を切り開く哲学対話の可能性を探る。

