部下の本音を引き出す!傾聴力(アクティブリスニング)を高めるには?(対話、マネジメント)傾聴力を高め、信頼関係を築き、組織を活性化させる
現代のビジネスで必須の傾聴力!管理職よ、部下の本音を引き出し、チームの成長を加速せよ。心理的安全性を高め、主体性を引き出す傾聴術とは? 共感的理解、自己一致、そして実践と振り返りが鍵。面談での質向上、雑談を通じた関係構築、そして「互聴」で組織を活性化! 新入社員育成にも効果的な傾聴スキルの全てを公開。あなたのコミュニケーションを劇的に変える、傾聴力向上プログラム!
傾聴を通じた信頼関係構築と組織活性化
上司が育成で最も大切なことは?
部下との信頼関係構築と傾聴力の向上。
本章では、法政大学教授の宮城まり子氏が提唱する「互聴」を通じた信頼関係構築の重要性について解説します。
組織における傾聴の役割について理解を深めます。

✅ この記事は、法政大学教授の宮城まり子氏が提唱する、職場での「互聴」を通じた信頼関係構築の重要性について解説しています。
✅ コミュニケーションは「情報の共有」「意思の共有」「気持ち・感情の共有」から成り、特に「気持ち・感情の共有(共感)」が重要であると述べ、適切な方法選択がコミュニケーションの質を左右すると指摘しています。
✅ コミュニケーションスキル、特に「ヒューマンスキル」は立場に関わらず重要であり、相手との信頼関係を築き、人を動かす根本的なスキルであると強調しています。
さらに読む ⇒『日本の人事部』 - HRで会社を伸ばす出典/画像元: https://jinjibu.jp/hr-conference/report/r201611/report.php?sid=866「互聴」という言葉、初めて聞きました。
上司と部下の間で、お互いに話を聞き合うってことですよね。
信頼関係を築くために、とても大切なことだと思います。
組織の価値を最大化するためには従業員の成長が不可欠であり、そのために上司による育成が重要となります。
特に中小企業においては、部下との信頼関係構築が育成の鍵となるため、上司は傾聴力を高める必要があります。
傾聴力は、チームの心理的安全性を高める土台となり、個々人の責任感や関心度を高め、生産性向上や人材定着率アップに繋がる。
上司が積極的に部下に関心を持ち、コミュニケーションの機会を増やすことで、部下の心理的安全性を高め、より良い関係性を築くことができます。
宮城まり子氏が提唱する「互聴」は、面談の質を向上させ、部下のキャリア開発・モチベーション向上、そして組織活性化に繋がります。
面談の質は、事前の準備と関係性の質に左右され、日ごろのコミュニケーション量の確保、心理的安全性のある関係性の構築、部下育成への意識が重要です。
上司は傾聴の姿勢を持ち、部下に関心を持ち観察し、メモを取り面談に活かす必要があります。
上司は傾聴の姿勢を持ち、部下に関心を持ち観察し、メモを取り面談に活かす必要があります。
積極的に声をかけ、部下の話を聴くことが重要です。
面談では、話の3要素(事実、気持ち、希望)を整理し、上司と部下がお互いの課題を整理し合うことが重要です。
上司の人たちも大変ねぇ。部下の話を聞いて、メモ取って、面談して…でも、それが組織を活性化させるって言うんだから、すごいわ。
部下の本音を引き出す、具体的な対話と対応
傾聴スキルで何が変わる?部下のやる気UPの秘訣とは?
安心感を生み、仕事意欲を向上させます。
本章では、部下の本音を引き出すための具体的な対話と対応について解説します。
相談モードと仕事モードを区別し、共感に基づき話を聞くためのテクニックを紹介します。
公開日:2024/11/07
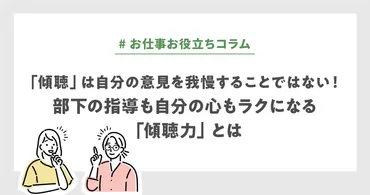
✅ 上司が部下の話を傾聴する際には、相手の相談モードと仕事モードを区別し、共感に基づき話を聞くことが重要である。
✅ 傾聴する際は、「同感」ではなく「共感」を使用し、自分の意見を押し殺すのではなく、心の中に留めておくことが大切である。
✅ 傾聴のテクニックとして、相手の反応に気を配りながら確認作業を重ね、部下の本音を引き出すようなコミュニケーションを心がけることが有効である。
さらに読む ⇒Be myself~゛働く゛を私らしく~出典/画像元: https://bemyself.pasonacareer.jp/skill/skill-1193/相手の気持ちに寄り添いながら話を聞くって、すごく大事ですよね。
自分の意見を押し殺すっていうのは、難しいけど、意識してやってみたいです。
部下の話を聞く際に、アドバイスや邪魔をせずに、相手の気持ちに寄り添いながら話を聞くことが重要です。
部下が安心して話せる環境を作るには、傾聴スキルを意識することが不可欠であり、それによって部下の仕事への意欲を高め、より良い職場環境を構築できます。
部下の相談に対しては、自分の意見を押し殺すのではなく、一旦心の中に置いておくことが重要です。
話を聴きながら「自分と同じ考えだ」「自分とは違うな」と整理する「分けて聴く」ことも有効です。
また、沈黙時は焦らず、部下のペースに合わせて待つことも大切です。
部下からアドバイスを求められた場合、自分の経験や知識を共有しつつ、部下自身の考えを引き出すような質問を心がけましょう。
上司は傾聴の姿勢を持ち、部下にアドバイスを求められた場合は、部下の考えを引き出す質問を心がけながら、自分の経験や知識を共有することが重要です。
ふむ、部下の本音を引き出すか。俺ももっと、社員の本音を聞き出せるようにならないとな。こいつら、もっともっと金になるアイデア持ってるはずなんだ。
傾聴力の育成と応用
良好な関係を築く秘訣は?傾聴力向上で何が変わる?
傾聴力で良好な関係構築!組織成長にも貢献。
最終章では、傾聴力の育成と応用について解説します。
傾聴力を高めるための具体的な方法や、様々な場面での応用例を紹介し、実践的なスキルを習得します。
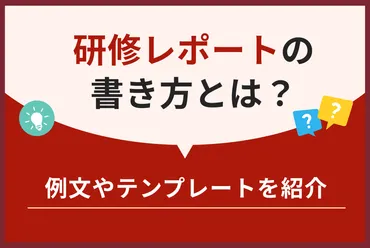
✅ 現代の管理職には、部下の話を深く聞き、理解する「傾聴力」が不可欠であり、自律を促すために重要である。
✅ 傾聴とは、相手の価値観を挟まずに話を受け止め、共感的理解、無条件の肯定的関心、自己一致の3つの要素を含む積極的傾聴(アクティブリスニング)の実践である。
✅ 傾聴力は、心理的安全性の高いチーム作り、部下の問題解決能力向上、キャリア自律の促進に繋がり、研修と実践と振り返りを繰り返すことで高めることができる。
さらに読む ⇒研修・人材育成サービス|企業研修・人材育成ならアルー出典/画像元: https://service.alue.co.jp/blog/how-managers-can-improve-their-listening-skills傾聴力って、社内だけじゃなくて、家族とか、いろんな人間関係に応用できるんですね!相手を理解しようとする姿勢…私も見習わなきゃ。
部下との良好な関係を築くためには、傾聴スキルを磨き、実践と振り返りを繰り返すことが重要です。
傾聴力は社内だけでなく、取引先や家族など身近な関係性にも応用可能であり、相手を理解しようとすることが良好な関係構築の第一歩となります。
管理職の傾聴力向上は、組織全体の成長に不可欠であり、そのための育成が重要です。
特に中小企業においては、部下との信頼関係構築が育成の鍵となるため、上司は傾聴力を高める必要があります。
適応課題(価値観や関係性の変革)と技術的課題(スキルの習得)の両面からのアプローチが求められます。
傾聴力は、相手を理解しようと積極的に話に耳を傾けるスキルであり、コミュニケーションや対話の質を向上させるために重要です。
例えば、新入社員との関係構築の事例や、OJT研修での傾聴の実践が、その効果を示しています。
相槌、アイコンタクト、ミラーリング、バックトラッキングといったテクニックを用いることで傾聴の効果を高めることができます。
あー、なるほどね!傾聴力って、色んな場面で使えるんだ。あたしも、もっと積極的に人の話聞いて、色んなこと吸収しよっかな!
本日の番組では、傾聴力の重要性、具体的な手法、そして組織における応用について解説しました。
傾聴力を高めて、より良い人間関係を築きましょう。
💡 傾聴力は、ビジネスだけでなく、日常生活においても重要なスキルです。
💡 傾聴力を高めるためには、実践と振り返りを繰り返すことが重要です。
💡 傾聴は、信頼関係を築き、組織を活性化させるための有効な手段です。


