ヒグマ問題、駆除は必要悪?人とヒグマの共存は可能か?(北海道・害獣問題)?2024年、過去最多の被害。増え続けるヒグマ被害と、駆除に対する様々な声。
過去最多の熊被害を受け、国は対策を転換。駆除への賛否が分かれる中、北海道の事例を基に、感情論ではなく現実的な視点での議論を呼びかける。駆除は必要なのか?共存は可能か?都市と地方の認識の差、そして現代社会の分断を浮き彫りにする。命を尊重する気持ちと、安全な暮らしを守るために必要な対策とは? 現場の苦労を理解し、持続可能な対策を模索する。
害獣駆除の現実と食料生産の重要性
害獣駆除にクレーム?食料生産と動物愛護、両立は可能?
人間が生きるため、害獣駆除は不可避です。
害獣駆除の現実と食料生産の重要性を見ていきましょう。
アライグマ駆除の現状と、都会からの安易なクレームに対する意見です。

✅ アライグマは法律で保護されており、無許可での駆除・捕獲は禁止されているため、被害に遭った場合は専門業者への依頼が必須。
✅ 駆除料金は被害状況によって変動し、簡易的な作業で5〜10万円、本格的な駆除で10〜30万円が相場。複数の業者から見積もりを取り、料金だけでなく作業内容やアフターサービスも比較検討することが重要。
✅ 業者選びでは、実績や評判の豊富さ、料金の明確さ、再発保証などのサービス内容を比較検討することが重要。
さらに読む ⇒マイナビ農業-就農、農業ニュースなどが集まる農業情報総合サイト出典/画像元: https://agri.mynavi.jp/2025_06_03_310674/アライグマの駆除費用は意外と高額ですね。
害獣駆除の現実を知ると、食料生産の大切さを改めて感じます。
駆除に対する感情論だけでなく、現実的な視点も重要です。
害獣駆除の現実を、著者は自身の経験や佐賀県在住の農家の声を通して訴えています。
都会の人間が実情を理解せず、動物愛護の観点から安易にクレームをつけることを批判し、人間が生きるために害獣駆除は不可避であると主張しています。
動物を食べる人間が、害獣駆除に反対するのは矛盾していると指摘し、食料生産の重要性を強調しています。
駆除以外の対策としては、旭山動物園での子熊保護や、電気柵の設置、緩衝エリアの整備などの地域対策が行われています。
北海道ではヒグマ管理計画も策定されており、個体数管理と共存への取り組みが重要です。
ほんと、都会の人は分かってないのよ!食べるからには、命をもらってるってこと、ちゃんと自覚しないとね。電気柵とか、できることからやらないと。
持続可能な対策と共存への道
クマ問題解決の鍵は?持続可能な対策とは?
生息数管理と環境整備の両立が重要。
持続可能な対策と共存への道を見ていきましょう。
政府の対策と、それに対する疑問点、そして持続可能な対策についての考察です。
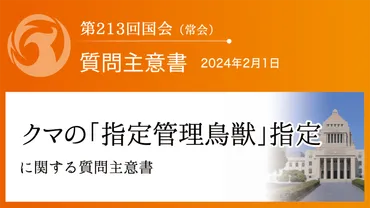
✅ クマによる人的被害増加を受け、政府はクマを「指定管理鳥獣」として捕獲費用を支援する検討を開始したが、捕獲だけでは根本的な解決にならないと指摘されている。
✅ 記事では、クマの生息環境悪化や生活圏と自然環境の分離の重要性、過去の駆除による絶滅の歴史などを踏まえ、捕獲に頼らない、より総合的な対策の必要性を訴えている。
✅ 政府に対し、クマの出没原因への対策、ゾーニング管理、生息環境調査、地域ごとの対策、指定管理鳥獣としての効果、共存に向けた対策、誘引物を用いた捕獲の問題点などについて質問している。
さらに読む ⇒参政党出典/画像元: https://sanseito.jp/2020/news/10220/長期的な視点に立った対策が必要ですね。
生息数調査の重要性や、YouTubeでの情報発信など、様々な取り組みが行われています。
共存への道は険しいですが、諦めずに努力していく必要があります。
被害増加の背景には、過疎化や高齢化による地域社会の衰退、耕作放棄地の増加といった構造的な問題も存在します。
このため、国や自治体は里山再生の取り組みを強化し、クマとの共生を図る環境整備にも力を入れる必要があります。
持続可能な対策として、生息数管理と環境整備を両立させることが重要です。
個体数を正確に把握するために、国は都道府県の生息数調査への交付金を支援し、調査の回数や方法の統一を図ることで、過去の過剰捕獲による個体数減少を防止します。
また、熊との遭遇時の正しい知識も必要であり、YouTubeチャンネルでの情報発信も行われています。
うむ、ゾーニング管理、生息環境調査…これは、企業におけるリスクマネジメントにも通ずるものがあるな。問題の本質を見抜き、長期的な視点で対策を講じる。さすが、政府!
まとめと今後の課題
ヒグマ管理、本質は?現場判断を尊重し、何が大切?
現実・対策・理解・感謝。クレーマーに負けるな!
まとめと今後の課題について見ていきましょう。
ヒグマ管理の複雑さと、現場の判断を尊重することの重要性についてです。

✅ 北海道庁は、ヒグマによる人や農業への被害を防止するため、捕獲活動を行うハンターへの非難に対し、活動への理解を呼びかけています。
✅ 捕獲活動は、地域の安全を守るために不可欠であり、ハンターへの非難は、担い手確保の妨げになる可能性を指摘しています。
✅ ヒグマとの共生のためには、住民一人ひとりが対策を徹底し、いざという時に住民の安全を守るハンターの重要性を認識する必要があると訴えています。
さらに読む ⇒grape グレイプ出典/画像元: https://grapee.jp/1464612ヒグマ問題は、単なる駆除だけでは解決しない複雑な問題ですね。
現場のハンターの方々への理解と感謝を忘れずに、共存を目指していくことが大切です。
ヒグマ管理の複雑さを理解し、現場の判断を尊重することの重要性が訴えられています。
安全に自然を楽しむために、現実を受け入れ、必要な対策を講じ、現場で苦労している人々への理解と感謝を忘れないことが大切です。
そして、駆除に対する抗議や「かわいそう」という苦情が殺到する社会問題に対し、駆除の必要性を理解しないクレーマーへの皮肉を込めたメッセージで締めくくられています。
む、せやね。駆除へのクレームとか、ほんまに意味ないのにね。現場の人たち、大変やろうに。まあ、文句言うやつは無視や!
本日の記事では、ヒグマ問題の現状、駆除の必要性、そして共存への道を探りました。
感情論だけでなく、現実的な対策を講じることが重要ですね。
💡 ヒグマ問題は、単なる駆除だけでは解決しない複雑な問題であり、長期的な視点に立った対策が不可欠。
💡 住民一人ひとりが対策を徹底し、現場で苦労している人々への理解と感謝を忘れないことが重要。
💡 ヒグマとの共存のためには、現実を受け入れ、必要な対策を講じることが不可欠。


