生成AI、AI時代の生き方、社会学、メディア、AIとの対話について学ぶ―これからの時代を生き抜くヒントとは?AI、社会学、メディア…時代の羅針盤を探る
AI大衆化時代を徹底解剖!Microsoftと古市氏が語るビジネス活用と社会への影響、ChatGPT活用の新スキル、そしてデザイナーの登場。成田悠輔氏の講演、社会学者の探求、田原総一朗氏の“闘魂伝承”まで。古市氏が語るAIとの革新的な対話、思考の質向上、読書体験の変化。AIがもたらす未来を、多角的に捉えた必見イベント録!
社会学の探求:多様な視点と社会との架け橋
社会学ってどんな学問?その役割とは?
社会の新たな視点を提供し、普及を目指す学問。
古市憲寿氏の著書を通して、社会学の定義や役割、多様な視点について学びます。
社会学が私たちに提供する、新たな視点と希望に触れていきましょう。
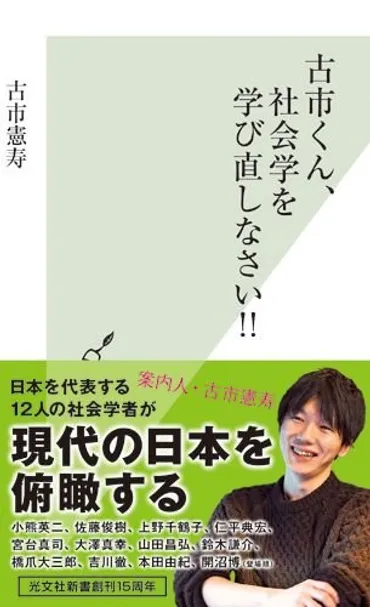
✅ 本書は、古市憲寿氏が12人の社会学者に「社会学とは何か」を尋ねた対話集であり、社会学の定義や考え方をわかりやすく解説している。
✅ 社会学は、普段私たちが当たり前と思っていることに対し、「なぜ?」「どうして?」と疑問を持ち、異なる視点を提供することで、問題の本質を明らかにする学問であると紹介されている。
✅ 本書は、社会学が社会を劇的に変えるものではないものの、多様な意見を受け入れ、新たな視点を探求する姿勢が、読者に希望を与え、行き詰まりを感じている人々に示唆を与える内容となっている。
さらに読む ⇒ダ・ヴィンチWeb出典/画像元: https://ddnavi.com/article/d334325/a/社会学の定義や役割について分かりやすく解説されていますね。
社会学が、私たちが当たり前と思っていることに疑問を投げかけ、多様な視点を提供するという点に共感しました。
古市氏と12人の社会学者との対談をまとめた書籍では、社会学という学問の探求と、その社会における役割が示されています。
法学や経済学など他の社会科学が扱えない領域を扱い、新たな視点を提供する社会学の定義が示され、社会学者の多様なスタンスと研究方法が紹介されています。
著者の古市氏は、メディアでの活動とアカデミアとの距離感を保ちながら、社会学と社会との橋渡し役としての可能性を示唆しています。
社会学者との対話を通じて、社会学の普及に貢献していくことが期待されています。
社会学って、難しそうだけど、面白いんですね!色んな考え方を知って、視野を広げたいなって思いました。
メディアへの闘魂伝承:期待と不安の交錯
田原総一朗氏の「闘魂伝承」への期待と不安、何が焦点?
若手論客への影響力と番組の将来性。
田原総一朗氏と若手論客の対談を通じて、メディアにおける闘魂伝承と、その期待と不安について考察します。
メディアの未来への希望と課題を探ります。
公開日:2013/08/28

✅ 田原総一朗氏が、TBSラジオの荻上チキ氏と、NHKの古市憲寿氏との対談を通じて、若手論客への「闘魂伝承」を行うと期待されている。
✅ 特に、荻上チキ氏との対談は、異なるタイプの論客同士の対決として注目されており、番組内での駆け引きが興味深い。
✅ NHKの「ニッポンのジレンマ」への出演は、番組の方向性に対する著者の疑問はあるものの、田原氏と古市氏の対談は両者にとって重要なものになると予想されている。
さらに読む ⇒アゴラ 言論プラットフォーム出典/画像元: https://agora-web.jp/archives/1555714.html田原総一朗氏の番組に関する期待と不安が入り混じった様子が興味深いですね。
番組の未来や後継者問題など、メディアを取り巻く状況が浮き彫りになっています。
一方、田原総一朗氏が荻上チキ氏、古市憲寿氏との対談を通じて、若手論客への「闘魂伝承」を行う週への期待と不安が表明されました。
TBSラジオ「Session-22」とNHK「ニッポンのジレンマ」への出演に注目が集まり、特に荻上チキ氏との対談に期待が寄せられました。
しかし、番組フォーマットの時代遅れ感や後継者問題、番組のリニューアルの必要性も指摘され、番組制作姿勢への疑問も呈されました。
田原氏の若手論客への影響力への期待と、自身の番組に対する複雑な思いが交錯する様子が描かれています。
田原さんの番組、いつも見てたからね。後継者問題とか、ちょっと寂しいけど、頑張ってほしいよね。応援してるよ!
AIとの対話:変化する情報収集と思考の進化
古市氏がAIと対話して得た最大のメリットは?
情報収集の効率化と思考の質向上。
古市氏がAIとの対話を通して感じた、情報収集と思考の変化について解説します。
AIとの新たな関係性について考察します。
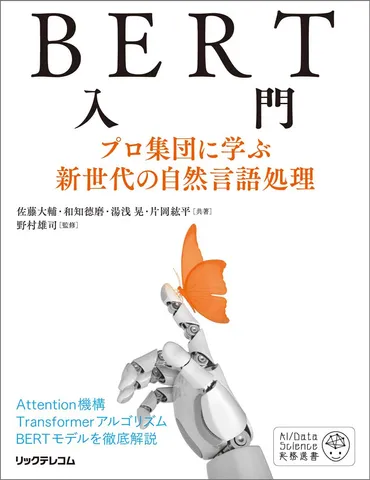
✅ BERTの登場により、自然言語処理(NLP)におけるAIのビジネス適用が加速し、新しい技術が生まれている。
✅ 本書は、Attention機構、Transformerアルゴリズム、BERTモデルを専門家集団が徹底解説し、現場で使えるコードも提供する。
✅ BERTを理解することで、新世代のNLP技術にキャッチアップできる。
さらに読む ⇒NTT DATA出典/画像元: https://www.nttdata.com/global/ja/about-us/profile/publication/2022/072601/AIとの対話を通じて、情報収集の質が向上し、思考の質も高まるというのは、非常に興味深いですね。
AIが単なる情報源を超え、思索のパートナーとなる未来を感じます。
古市氏がAIとの対話を通して、情報の収集方法が大きく変化したことについて言及しています。
AIの進化により、最新の研究に基づいた情報へのアクセスが容易になり、思考の質も向上したと述べています。
AIは単なる情報提供者としてだけでなく、思索のパートナーとしても機能し、たとえば、人間の身長が文明に与える影響についてAIと議論し、小型人類が創造するであろう猫神話まで生成してもらった経験が語られています。
AIとの対話は、場所を選ばず行われ、老眼人口の増加とも相性が良く、出版市場への影響についてもAIにレポート作成を依頼する予定である。
古市氏は、AIとの対話が読書時間の代替となっており、その利便性と可能性を高く評価しています。
AIとの対話で思考が進化するって、すごい時代になったね。老眼でもAIがレポート作ってくれるなら、私も試してみようかな。
本日の記事では、生成AIの活用、AI時代への適応、社会学の視点、メディアの変化、そしてAIとの対話についてご紹介しました。
変化の時代を生き抜くためのヒントが詰まっていますね。
💡 生成AIのビジネス活用事例や、AI時代の生き方に関するヒント、社会学による多様な視点について、具体的な情報を得ることができました。
💡 メディアの現状と未来、AIとの対話による情報収集と思考の変化、そして変化への適応について、深く考察することができました。
💡 AIの進化、社会の変化に対応していくために、私たち自身も学び続け、変化し続けることが重要であると改めて感じました。


