氷見市は大丈夫? 令和6年能登半島地震の爪痕地震からの復興とは!!!
令和6年能登半島地震、氷見市の被災状況と復興への道のり。断水や住宅被害、人口減少、そして地域再生に向けた取り組みを紹介。

💡 令和6年能登半島地震は、石川県氷見市を含む多くの地域に大きな被害をもたらしました。
💡 地震の影響で、氷見市では人口減少が深刻化しています。
💡 氷見市は、地震からの復興に向けた取り組みを進めています。
それでは、詳しく見ていきましょう。
地震の衝撃と住民たちの苦悩
能登半島地震後、氷見市姿地区の人口はどうなった?
10.7%減少
地震の影響は本当に深刻ですね。

✅ 能登半島地震の影響で、氷見市姿地区の人口が昨年末から今年11月末にかけて10.7%減少しました。これは、地震による住宅やインフラ設備の被害を受け、住民が市内外の他地域へ移住したためです。特に、姿地区は泥岩層にあり地震の揺れが伝わりやすく、多くの建物が被害を受けました。
✅ 被害が大きかった他の地区でも人口減少が顕著で、間島・新道地区は6.4%、北大町・栄町は6.1%減少しました。氷見市は、来年度策定する第3期まち・ひと・しごと創生総合戦略に人口減少対策を盛り込む予定です。また、企業誘致促進のため、企業立地助成金の交付基準を見直し、近隣市に負けないように制度設計するとしています。
✅ 市議会会派・自民同志会は、菊地市長に対して来年度の重点事項に関する要望書を提出しました。要望内容は、能登半島地震からの復旧復興に向けた財源確保、災害公営住宅・宅地液状化防止の整備、新たな幹線道路の整備、地方創生に向けた取り組みの推進、過疎地域の振興など10項目です。
さらに読む ⇒北國新聞出典/画像元: https://www.hokkoku.co.jp/articles/tym/1602483氷見市は、厳しい状況に直面していることがわかります。
令和6年能登半島地震は、石川県氷見市を含む多くの地域に大きな被害をもたらしました。
地震直後から、氷見市姿集落農事集会所には多くの住民が避難し、特に高齢者は指定避難所までの移動が困難なため、集会所が避難所として開放されました。
また、市中心部の北大町では、長引く断水により、自宅で風呂に入れず困っている住民の姿が見られました。
地震から1週間が過ぎても、被災地では生活再建への道のりは長く、住民たちの不安や悲しみは募っていました。
地震による住宅やインフラ設備の被害は深刻で、特に姿地区では泥岩層にあり、地震の揺れが伝わりやすかったため、大きな被害を受けました。
その結果、姿地区の人口は昨年末から今年11月末にかけて10.7%減少しました。
住民の多くが市内外へ移住したことが原因です。
氷見市は、泥岩層なんだな。だから揺れが大きかったのか。
復興への道のり 住民と行政の連携
被災地の復興に向け、様々な動きが出ていますが、具体的な取り組みは?
住宅支援、移住支援、企業誘致など
復興に向けて、具体的な取り組みが始まっているんですね。
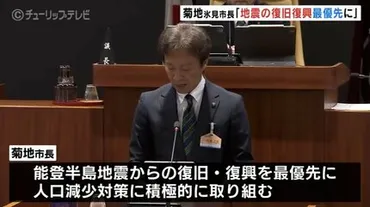
✅ 氷見市議会12月定例会が開会され、菊地正寛新市長は所信表明を行い、能登半島地震からの復旧・復興に「スピード感をもって取り組む」と述べました。
✅ 菊地市長は、人口減少対策にも積極的に取り組む姿勢を示し、復興の先にある未来に向けて、活力に溢れ、安全で安心なまちを目指すと表明しました。
✅ 今回の定例会では、能登半島地震災害関連費用を含む6億243万円の補正予算案が提出され、12月9日から代表質問が始まります。
さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tut/1595064?display=1市長も復興に強い意欲を持って取り組まれていることが伝わってきます。
被災地では、生活再建に向けた取り組みが始まりました。
姿地区では、住民でつくる「姿復興の会」が、新規住宅着工時の地盤改良補助や市外からの移住支援などを市に求めています。
一方、市議会では、働く若い女性確保に向けた企業誘致を求める声があり、市は企業立地助成金の交付基準を見直すことを表明しました。
さらに、自民同志会は、菊地市長に対して、能登半島地震からの復旧復興に向けた財源確保、災害公営住宅や宅地液状化防止の整備、新たな幹線道路整備など10項目の要望書を提出しました。
氷見市は、将来へ向けて人口減少対策も進めていくんですね。
断水に見舞われた街 水を求める人々
地震で何が断水した?
水道が止まった
断水は本当に大変ですね。
公開日:2024/01/05

✅ 富山県は、地震による重軽傷者数が36人から37人に修正され、避難者数は高岡市、氷見市、射水市の順で多い。
✅ 断水は氷見市を中心に9179戸で続いており、氷見市、高岡市、小矢部市では応急給水が行われている。
✅ 陸上自衛隊は氷見市の避難者に炊き出しを行う予定で、JR氷見線は6日始発から運転を再開する見込み。
さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASS147T98S14PISC008.html復旧のめどが立たないのは不安ですね。
地震の影響は、水道供給にも及びました。
石川県内の氷見市、高岡市、小矢部市など5市で断水が発生し、氷見市では全域で水道が使えなくなりました。
給水場には長蛇の列ができ、住民はポリタンクやペットボトルを持って、飲み水を求めていました。
断水の原因は不明で、復旧のめどは立っていません。
市は水道管の調査を進めていますが、大きな漏水箇所は見つかっておらず、原因特定を急いでいます。
水がないのは困るわよね。
人口減少の危機 姿地区の未来
氷見市姿地区の人口減少の主な原因は?
地震による被害
地震の爪痕が深く、厳しい状況が続いているんですね。
公開日:2024/03/10

✅ 富山県氷見市姿地区は能登半島地震で大きな被害を受け、1カ月以上経過しても崩れた家屋が放置され、道路が塞がれている状況です。
✅ 救急車が通れない道路もあり、地震の爪痕は大きく、引っ越す意向の住民もいるため、地区の将来は不透明です。
✅ 姿地区の姿公民館は最後の避難所となっており、高齢者が多い地区では、地震発生前に69世帯151人が住んでいましたが、2月7日時点で15世帯のみが居住している状況です。
さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20240209/k00/00m/040/158000c姿地区の未来は不透明ですが、復興への道のりを歩んでほしいですね。
地震により、氷見市姿地区の人口は減少傾向にあります。
地震による住宅やインフラ設備の被害を受け、住民が市内外の他地域に移住したことが原因です。
姿地区は泥岩層にあり、地震の揺れが伝わりやすかったため、今後も人口減少が進む可能性があります。
市は、姿地区への移住支援など、人口減少対策を盛り込んだ第3期まち・ひと・しごと創生総合戦略を来年度に策定する予定です。
氷見市は、人口減少対策をしっかりとして、姿地区の活性化につなげないとな。
復興へのロードマップ 未来への歩み
能登半島地震からの復興、どんなロードマップで進む?
5つの柱で段階的に推進
復興への道は長く、大変な道のりですが、。
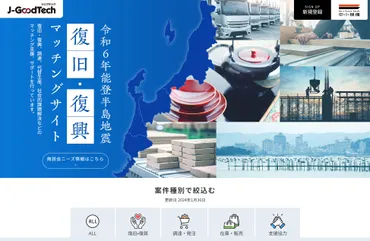
✅ 中小企業基盤整備機構は、能登半島地震で被災した中小企業の事業再開支援のため、「復旧・復興マッチングサイト」を開設しました。
✅ 同サイトでは、被災企業の復旧・復興ニーズと全国の企業を繋ぎ、再建に必要な人材や物資、技術などのマッチングを支援します。
✅ 中小機構は、マッチングの成約や事業再開までのサポートに加え、被災企業の再建に向けたアドバイスや事業計画作成支援など、総合的な支援を提供していきます。
さらに読む ⇒PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001412.000021609.htmlロードマップに基づいて、着実に復興を進めていけば、必ず未来は開けるでしょう。
「令和6年能登半島地震」からの復旧・復興に向け、市民生活再建、インフラ再構築、地域産業再生、情報収集・広報、地域防災力向上という5つの柱を軸とする「被災者支援・復旧復興ロードマップ」が作成されました。
このロードマップは、市役所全体でスピード感を持って取り組み、被災地区の課題・ニーズを捉えながら随時更新していくことを基本としています。
県との連携を重視し、国の支援も活用しながら、復旧・復興を段階的に進め、長期的な発展につなげることを目指しています。
氷見市は、復興に向けて様々な支援を受けながら、未来へ向けて進んでいくんですね。
令和6年能登半島地震は、氷見市に大きな爪痕を残しました。
しかし、復興への取り組みは着実に進んでおり、未来への希望も見え始めています。
💡 令和6年能登半島地震は、氷見市に大きな被害をもたらしました。
💡 地震の影響で、氷見市の人口は減少傾向にあります。
💡 氷見市は、地震からの復興に向けた取り組みを進めています。


