校閲ってどんな仕事?〜校閲の基本からスキルアップまで徹底解説!〜校閲のプロフェッショナル
誤字脱字チェックだけじゃない!書籍やWebコンテンツの質を格段に上げる校閲・校正の世界へ。内容の正確性、表現の適切さ、法的問題まで見抜くプロの技を解説。校正との違い、校閲者の仕事内容、必要なスキル、キャリアパス、そして最新のAIとの連携まで網羅。新潮社校閲部のオンライン講座情報も。文章表現に自信がないあなたも、この情報で一歩踏み出せる!
校閲の具体的な作業内容
校閲、一体何するの?内容、表現、全部チェック!
誤字脱字から表現まで、文章を徹底的にチェック!
表記統一は、文章全体の統一感を出すために非常に重要な作業です。
表記揺れを修正し、読者が読みやすい文章を作成します。
出版社や企業が作成した表記統一表を参考にします。
![文章の表記統一[表記ゆれを正す際に知っておきたい基本ルール]](https://diamond-edge.com/imgs/de/25141/3.webp)
✅ 表記統一は、文章内の表記の揺れ(表記ゆれ)を修正し、統一感を持たせる作業であり、出版社や企業が作成する表記統一表を参考に校正者が行います。
✅ 表記統一表がない場合や、表にない用語が出てきた場合は、文章内での出現頻度を参考に統一したり、辞書や用字用語辞典を参照したりして対応します。
✅ 表記統一をする際には、意図的な使い分けがある場合もあるため、機械的にどちらかの用語に揃えるのではなく、文脈を理解して判断することが重要です。
さらに読む ⇒校正視点|校正・校閲の専門サイト出典/画像元: https://kousei.club/notation-of-text/表記の統一は、文章の読みやすさに大きく影響するんですね。
表現の揺れをなくすことで、読者の理解度も高まると思います。
校閲は、単に文字や文章の誤りを正すだけでなく、内容の整合性、事実関係、文章のニュアンスまで深くチェックする重要な作業です。
専門知識も必要となるため、社内関連部署や制作会社との連携が不可欠です。
具体的には、同音異字や誤変換、慣用句の誤用、送り仮名、句読点による意味の違い、主述のねじれなどをチェックします。
さらに、トーン&マナーや表現を整えることも重要で、表記の統一、長い文章やわかりにくい文章の修正、文語・口語、常体・敬体の統一、敬語の間違いの修正、単調な表現の回避などを意識します。
指示語や接続詞、冗長な表現の使いすぎにも注意し、常用漢字表に基づいた表記を用いることで、より読みやすい文章を目指します。
文章の表現を統一するって、ものすごく細かい作業だけど、読みやすさにつながるんだね。いつも何気なく読んでたけど、すごいなぁ。
校正と校閲の関係とキャリアパス
校正の仕事ってどんなこと? 必須スキルは?
誤字脱字チェック、集中力、知識など。
校正と校閲は密接な関係があり、両方の業務を兼ねることが多いです。
校正者は、誤字脱字や体裁をチェックし、必要に応じて内容の確認も行います。
校正・校閲のキャリアパスについてご紹介します。
公開日:2021/06/07
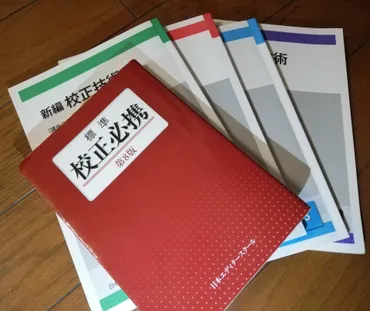
✅ 校正者は、印刷物の誤字脱字、体裁、印刷上の不備をチェックする「校正」と、内容の矛盾や事実誤認、固有名詞の誤りなどをチェックする「校閲」の両方の業務を担うことが多い。
✅ 一般的には「校正者」という名称で両方の業務が行われるが、新聞社や大手出版社では「校閲記者」や「校閲部」という専門の部署が存在する場合もある。
✅ 校正の仕事を受ける際には、「校正」と「校閲」のどちらの範囲まで担当するのかを事前に確認することが重要である。
さらに読む ⇒校正まるめがね出典/画像元: https://kouseimarumegane.com/kousei-kouetsu/校正と校閲、どちらの仕事も、文章の品質を保つ上で重要ですね。
専門知識を活かして、活躍できる場が広がっていることも魅力的です。
校正の仕事は、執筆者の原稿の誤字脱字や用語の不統一をチェックすることであり、校閲と密接な関係があります。
校正の雇用形態は、出版社や校正プロダクション、Webメディアへの依頼などがあります。
校正の仕事内容は、誤字脱字、文法の間違い、文章の矛盾などを1文字単位で確認し、必要に応じて辞書などで用語を調べます。
校正に必要なスキルとして、集中力、忍耐力、探究心、日本語能力、幅広い知識などが挙げられます。
校正記号の知識や、Wordなどのアプリケーションスキルも重要になります。
校正者の年収は、20代で約368万円、30代で約496万円ですが、フリーランスの場合は、文字単価で料金が決まります。
キャリアパスとしては、専門分野を極めたり、校閲者になる道があります。
校正技能検定という資格もあります。
校正と校閲のキャリアパスか。自分の専門性を高めて、更なる高みを目指すのも良いし、フリーランスで自分のペースで仕事をするのも悪くないな!
校閲スキルを向上させるための取り組み
校閲スキルを爆上げ!新潮社の講座、どんな内容?
校閲の基礎からAI連携まで、実践スキル習得!
校閲スキルを向上させるための取り組みとして、新潮社校閲部の甲谷允人氏によるオンライン講座をご紹介します。
実践的な校閲問題を解き、現役校閲者の視点から解説を受けることで、スキルアップを目指します。
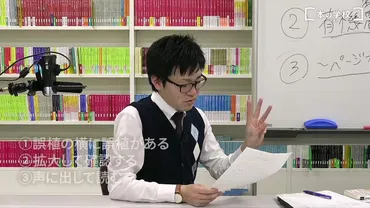
✅ 新潮社校閲部の甲谷允人氏が、校閲の仕事内容、iPad校閲、AIとの連携など、最新のトピックを交えて解説するオンライン講座。
✅ 講座では、校閲の実践問題を通じて校閲のポイントを学び、現役校閲者の視点から失敗例や成功例、表記統一、差別表現など、現場で役立つ情報が提供される。
✅ 未経験者から経験者まで幅広く受講可能で、校閲例の解説、レジュメに基づいた講義、アーカイブ動画の視聴を通して、校閲の知識とスキルを習得できる。
さらに読む ⇒新潮社 本の学校出典/画像元: https://hon-gakko.com/lecture_page/%E6%96%B0%E6%BD%AE%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%A0%A1%E9%96%B2%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E8%AC%9B%E5%BA%A7%EF%BC%88%E5%89%8D%E7%B7%A8%EF%BC%89-%E6%A0%A1%E9%96%B2%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86/オンライン講座で、プロの校閲者から直接指導を受けられるのは、とても魅力的ですね。
実践的な問題を通して、スキルを磨けるのも良いですね。
新潮社校閲部の甲谷允人氏によるオンライン講座が開催されており、校閲の基礎から最新の技術動向までを網羅し、校閲者を目指す方から経験者まで幅広く対象としています。
講座では、校閲の仕事内容、注意点、iPad校閲の実演、AIとの連携など、最新のトピックも扱います。
受講者は事前に校閲問題を解き、動画内で解説を受けることで、実践的なスキルを習得できます。
本講座は、校閲例の解説と講義の2部構成で、アーカイブ動画は原則として何度でも視聴可能です。
新潮社校閲部のベテラン社員がチェックした実践的な校閲問題を通して、校閲スキルを向上させることを目指します。
オンライン講座でスキルアップ…いいんじゃない?あたしも、もっと文章上手くなりたいし、受けてみようかな!
本日は校閲という仕事について、様々な角度からご紹介しました。
誤りのない情報を届けるために、校閲者の努力は欠かせませんね。
💡 校閲は、誤字脱字の修正だけでなく、内容の正確性を担保する重要な仕事である。
💡 校閲者には、専門知識、調査力、そして文章を客観的に評価する能力が求められる。
💡 校閲スキルを向上させるための講座や情報源は豊富にあり、学び続けることが大切である。


