岐阜県の地震対策は?過去の地震と防災計画を徹底解説?岐阜県の地震リスクと減災対策
岐阜県は地震リスクに直面!内陸型地震と南海トラフ巨大地震の脅威。過去の教訓から、活断層の直下型地震や南海トラフ地震への対策を強化。県民の生命を守るため、家具固定や耐震補強などの備えを呼びかけます。最新の地震情報も公開!
過去の地震からの教訓と複合災害への備え
岐阜を襲った過去の地震とは?最大の被害は何?
濃尾地震。5万棟以上全壊、約4990人死亡。
過去の地震の教訓を活かした備え、とても大切ですね。
防災アイテムを揃えておくこと、私もすぐに始めたいと思います!。
公開日:2019/03/09

✅ 2018年10月に岐阜県で発生した地震は、過去の濃尾地震の震源に近い断層集中地帯で発生しており、日本アルプス周辺は地殻変動が活発な地域であると解説されています。
✅ 地震発生に備えて、簡易トイレや防臭袋、ヘッドライト、ポータブル電源、ソーラーチャージャー、浄水器、カセットガスボンベ、テントなどの防災アイテムを備えておくことが推奨されています。
✅ 記事では、これらの備災アイテムを具体的に紹介し、amazonでの購入を促しています。
さらに読む ⇒ITOITO-STYLE(いといとスタイル)出典/画像元: https://itoito.style/article/4996過去の地震の被害の大きさに、言葉を失います。
これらの教訓を活かして、日々の生活でできる備えをしっかりとしていきたいです。
岐阜県では、過去の内陸型及び海溝型地震によって大きな被害が発生しました。
1891年の濃尾地震(M8.0)は国内最大規模の内陸活断層型地震で、5万棟以上の建物が全壊し、約4990人もの死者を出しました。
また、1858年の飛越地震(M7.0~7.1)では飛騨地方で家屋倒壊が深刻化し、岐阜県全体で319棟が全壊、203人が犠牲となりました。
1946年の昭和南海地震 (M8.0) では、津波の被害はなかったものの、県内で300棟以上の建物が全壊し、32人の方が犠牲になりました。
これらの過去の地震の教訓を活かし、岐阜県地域防災計画が策定されています。
地震だけでなく、風水害や土砂災害のリスクもあり、浸水想定区域マップの活用や、土砂災害危険区域の確認も推奨されています。
昔の地震の話を聞くと、改めて防災って大事だって思うわ。amazonで防災アイテム、私も買ってみようかしら。
地震防災行動計画と減災対策
岐阜県の地震対策、目指すは?
災害死ゼロ!5年間の減災対策です。
地域コミュニティの活性化が、防災にも繋がるというのは素晴らしいですね。
具体的にどのような活動が行われているのでしょうか?。
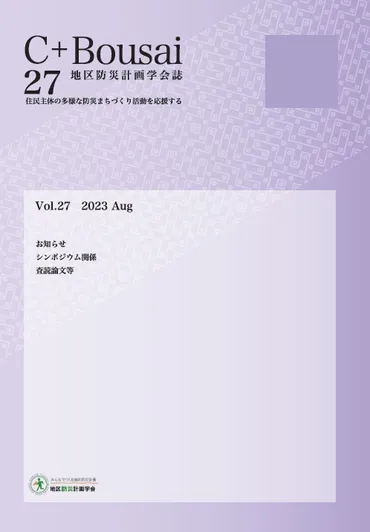
✅ この記事は、地域コミュニティの活性化を目指す活動について述べており、企業や市民との連携、継続的な取り組みの重要性を強調しています。
✅ 具体的な取り組みとして、防災イベントの開催や、コミュニティ形成のためのプラットフォームの構築、NPOとの連携などを紹介しています。
✅ 記事内では、過去の防災イベントの実施状況や、関連するウェブサイトへのリンクも提示されています。
さらに読む ⇒nhЌvwbgbv出典/画像元: https://gakkai.chiku-bousai.jp/papers01.html減災対策の計画が策定されているのは心強いですね。
能登半島地震の教訓も活かされているとのこと、今後の取り組みに期待したいです。
岐阜県では、地震による災害死ゼロを目指し、地震に対する予防、応急、復旧・復興の3つの時系列別の減災対策を総合的に推進する「第五期岐阜県地震防災行動計画」が策定されています。
この計画は、令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間とし、令和6年能登半島地震を踏まえた震災対策の見直しと第3期岐阜県強靱化計画に位置づけた地震防災対策が反映されています。
計画策定にあたっては、パブリックコメントが実施され、その結果も公表されています。
第五期計画では、県民の生命保護、県の機能維持、財産及び公共施設被害の最小化、迅速な復旧復興を基本目標としています。
効果的な減災対策のためには、地域全体での連携が不可欠です。企業も積極的に参加すべきでしょう。
地震情報の公開と県民の備え
岐阜県の地震、過去の教訓から何を学ぶ?
備えあれば憂いなし!家具固定と耐震を。
地震に関する情報公開は、県民の意識を高める上で非常に重要ですね。
日頃から情報をチェックする習慣をつけたいと思います。

✅ 2024年1月15日18時37分頃、岐阜県美濃中西部を震源とする地震が発生しました。
✅ 地震の規模はマグニチュード2.8、深さ約20kmで、最大震度1を岐阜県輪之内町で観測しました。
✅ この地震による津波の心配はありません。
さらに読む ⇒日本気象協会 tenki.jp - tenki.jp出典/画像元: https://earthquake.tenki.jp/bousai/earthquake/detail/2024/01/15/2024-01-15-18-37-46.html過去の地震の発生状況をみると、改めて地震の恐ろしさを感じます。
日々の備えの大切さを再認識しました。
岐阜県における地震活動は、気象庁が毎月発行する「地震概況」で情報が公開されています。
2024年6月から2025年5月までの地震概況が提供され、県内の地震活動に関する詳細なデータを確認できます。
岐阜県では、2020年代に2024年1月1日の石川県能登地方を震源とする地震(M7.6)で震度5弱を観測しました。
1940年代には、1946年の和歌山県南方沖地震と1944年の三重県南東沖地震で震度5を観測しています。
1920年代から2020年代までの震度5以上の地震発生回数は合計3回、震度1以上の地震は合計1483回発生しています。
これらのデータに基づき、県民は地震への備えとして、家具の固定や建物の耐震補強を行い、自らの命を守ることが重要です。
震度5以上の地震が3回か…やっぱり、いつ起きてもおかしくないんだね。備えあれば憂いなし、っていうから、ちゃんと対策しとかないとね。
本日の記事では、岐阜県の地震リスクと、私たちができる対策について詳しく解説しました。
日々の備えが大切ですね。
💡 岐阜県は、活断層と南海トラフ地震という2つの地震リスクに直面しており、過去に大きな被害を受けている。
💡 地震による被害を最小限に抑えるため、岐阜県は地震防災行動計画を策定し、様々な減災対策を推進している。
💡 県民は、日頃から防災意識を高め、家具の固定や非常用持ち出し袋の準備など、自らの身を守るための対策を行うことが重要である。


