和辻哲郎文化賞とは?受賞作品や記念講演会について徹底解説!(?)姫路市が主催する和辻哲郎文化賞、受賞者と授賞式、記念講演会情報
姫路市が誇る「和辻哲郎文化賞」!文学、歴史、芸術…幅広い分野から優れた著作を表彰。今年は平井健介氏の『日本統治下の台湾』と鷲田清一氏の『所有論』が受賞!授賞式は3月2日、作家・岩下尚史氏の講演も。過去には司馬遼太郎氏らも選考委員を務め、各界に影響を与えてきた。文化への深い理解を促す、魅力的な賞の歴史と未来。
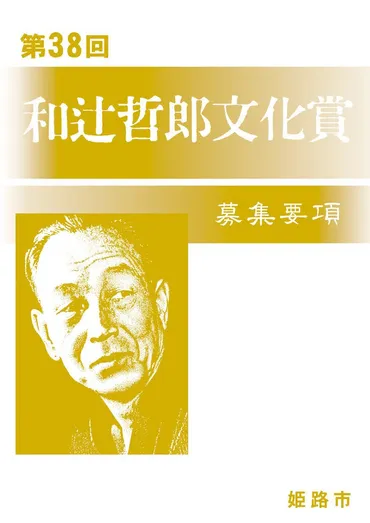
💡 姫路市が主催する文学賞「和辻哲郎文化賞」について、その概要と目的を解説します。
💡 第37回和辻哲郎文化賞の受賞者と受賞作品、選考委員について詳しくご紹介します。
💡 授賞式典や記念講演会の詳細と参加方法、過去の受賞作についても触れます。
それでは、和辻哲郎文化賞の歴史と概要から見ていきましょう。
姫路市と和辻哲郎の足跡
姫路市が創設した和辻哲郎文化賞、対象は?
文学、歴史、芸術などの優れた著作
和辻哲郎文化賞の創設背景や、賞の目的について掘り下げていきます。
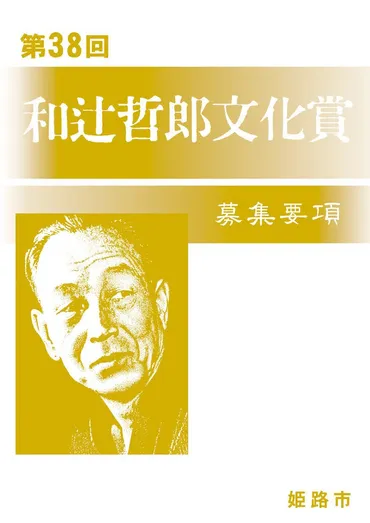
✅ 和辻哲郎の業績を顕彰するため、姫路市が創設した文化賞で、一般部門と学術部門があり、受賞者には正賞と副賞が贈られる。
✅ 選考は、関係機関からの推薦を受け、予備選考を経て選考委員会が受賞作を決定する。
✅ 第38回は令和7年9月3日締切で、令和8年2月上旬に受賞作発表、3月1日に授賞式が行われる。
さらに読む ⇒PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000286.000073910.html和辻哲郎の功績を讃え、文化の発展に貢献するこの賞は素晴らしいですね。
1988年、兵庫県姫路市は市制百年と哲学者・和辻哲郎の生誕百年を記念し、和辻哲郎文化賞を創設しました。
この賞は、和辻哲郎の多岐にわたる学問分野への貢献を顕彰し、文学、歴史、芸術など幅広い分野における優れた著作を対象としています。
和辻哲郎は明治22年(1889年)に姫路市で生まれ、東京帝国大学で哲学を学び、ニーチェ研究から出発、後に東洋思想にも関心を深めました。
『古寺巡礼』や『風土』『倫理学』など、日本思想界に大きな影響を与えた人物です。
和辻哲郎文化賞、素晴らしいですね!歴史と重みが違いますね。姫路市も粋なことしますね!
第37回和辻哲郎文化賞:選出と内容
和辻哲郎文化賞、今年の受賞作は?
平井健介氏と鷲田清一氏の著作です。
第37回和辻哲郎文化賞の受賞者の作品内容をさらに詳しく見ていきましょう。
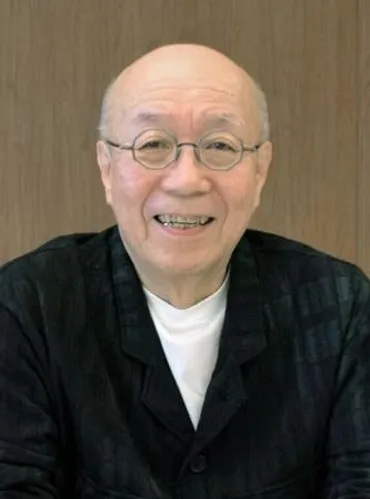
✅ 兵庫県姫路市が主催する第37回和辻哲郎文化賞の受賞者が発表され、一般部門は平井健介氏、学術部門は鷲田清一氏に決定しました。
✅ 平井健介氏は著書「日本統治下の台湾―開発・植民地主義・主体性―」で、日本統治時代の台湾史を多角的に考察し、鷲田清一氏は著書「所有論」で「所有」という概念を多面的に分析したことが評価されました。
✅ 授賞式は、姫路市市民会館で3月2日に開催される予定です。
さらに読む ⇒山陽新聞デジタル|さんデジ出典/画像元: https://www.sanyonews.jp/article/1675416受賞作は、現代社会の課題に鋭く切り込んだ素晴らしい作品ばかりですね。
第37回和辻哲郎文化賞の受賞作が決定しました。
一般部門では、甲南大学経済学部の平井健介教授による『日本統治下の台湾―開発・植民地主義・主体性―』が、学術部門では、大阪大学名誉教授の鷲田清一氏による『所有論』がそれぞれ受賞しました。
平井氏の著作は、日本統治下の台湾における開発や植民地主義、主体性について深く考察しており、鷲田氏の『所有論』は、現代社会における所有の概念を検証しています。
選考委員は、一般部門に辻原登氏、山内昌之氏、ロバートキャンベル氏、学術部門に清水正之氏、野家啓一氏、関根清三氏が務めました。
鷲田氏は、自身の著作が和辻哲郎の研究に影響を受けていると述べ、今回の受賞を喜んでいます。
平井さん、鷲田さん、受賞おめでとうございます!お二人の作品、ぜひ読んでみたいですね。
次のページを読む ⇒
和辻哲郎文化賞授賞式が姫路で開催!岩下尚史氏の記念講演も。多様な視点を提供する賞の歴史と、未来への期待。詳細をチェック!

