能登半島地震と豪雨、二重の苦難に見舞われた被災地を追う。復興への道のりは?(輪島市、珠洲市)能登半島北部、地震と豪雨による二重の被害と、復興への取り組み
能登半島地震から8ヶ月半後、記録的な豪雨が輪島市と珠洲市を襲い、被災者を二重の苦難に。仮設住宅浸水、支援の遅れ…復興への道のりは険しい。それでも、輪島市は復興計画を策定し、市民参加で持続可能な復興を目指す。JPFやNGOによる支援、公費解体制度、被災状況の写真公開など、復興への取り組みを詳細に伝える。

💡 2024年の能登半島地震と、その後の豪雨によって輪島市と珠洲市を中心に甚大な被害が発生しました。
💡 復興に向けて、市民と行政が様々な計画を策定し、市民参加型の取り組みが進められています。
💡 公的支援制度として、被災家屋の解体・撤去に関する手続きが進められており、NGOによる緊急支援も行われています。
それでは、今回の記事で皆様に知っていただきたい3つのポイントをご紹介します。
二重の悲劇 連続する災害がもたらす苦難
能登半島を襲った豪雨、被災者の苦難は?
地震と豪雨の二重被害で、避難生活が長期化。
今回の記事では、能登半島地震と豪雨による被災地の状況、復興への道のり、そして公的支援について詳しく見ていきます。

✅ 能登半島地震における津波被害は、石川県珠洲市では広範囲に及んだ一方、輪島市では地盤隆起の影響でほとんど発生しなかった。
✅ 珠洲市では最大3メートルの津波が内陸400メートルまで達し、家屋の流失や損壊を引き起こした一方、輪島市では1.2メートル以上の津波を気象庁が観測したものの、大きな被害は確認されなかった。
✅ 今回の調査結果から、ハザードマップの重要性が改めて示され、被災地以外の地域でもハザードマップの確認を促している。
さらに読む ⇒中日新聞Web出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/834017地震の被害に加え、豪雨による更なる被害は、被災者の方々の心に深い傷跡を残しました。
二重の災害は、想像を絶する苦難だったと思います。
2024年1月1日に発生した能登半島地震は、マグニチュード7.6、最大震度7を記録し、甚大な被害をもたらしました。
地震から8カ月半が経過し、道路復旧が進む中、2024年9月21日からの記録的な豪雨が能登半島北部を襲いました。
輪島市では498.5mm、珠洲市では393.5mmの48時間雨量を記録し、平年の9月1ヶ月分の2倍以上の雨量となりました。
この豪雨は、地震で大きな被害を受けた輪島市と珠洲市を直撃し、二重の苦難をもたらしました。
被災者の住まいの再建は遅れ、先の見えない不安が広がっています。
輪島市門前町浦上の菜畑隆司さん夫妻や、輪島市宅田町の狭間三子雄さんのように、地震で全壊した自宅を諦め仮設住宅に入居した矢先に豪雨に見舞われ、さらなる被害を受けた人々は、精神的な負担を増大させています。
仮設住宅の床上浸水などにより、さらなる避難生活を余儀なくされる住民も多く、行政による支援の遅れも課題となっています。
これは酷い話だ。地震で家を失った上に、豪雨で仮設住宅まで浸水とは。行政の支援は急務だな。
復興への道のり 市民と行政の取り組み
輪島市の復興、最大のポイントは?
市民参加と隈研吾氏の専門性
復旧・復興に向けた、輪島市の取り組みを評価しつつ、計画の透明性や市民参加の重要性を感じます。
公開日:2024/06/01
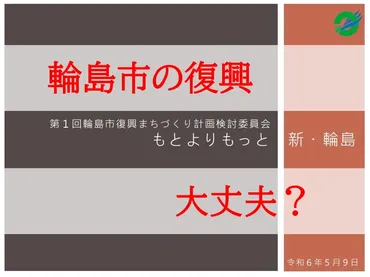
✅ 輪島市が公開した復興まちづくり計画資料に対し、隈研吾氏の委嘱期間の短さや計画策定期間のタイトさ、計画概要の物足りなさなど、複数の疑問点を提起し、改善を提案しています。
✅ 隈研吾氏の復興への積極的な姿勢を尊重しつつ、リモート参加でも良いので、計画への継続的な関与を要望。また、石川県の復興プランを参考に、長期的な視点での計画策定を提案しています。
✅ 市民意見の反映を評価しつつ、スケジュール上の矛盾点を指摘。市民意向調査の結果報告時期やパブリックコメントの結果報告時期などを明確化し、より透明性の高い計画策定を求めています。
さらに読む ⇒輪島たいむす出典/画像元: https://wajimatime.hatenablog.com/entry/2024/06/01/160315隈研吾氏のデザインは素晴らしいですが、市民の声がちゃんと反映される形で進んでほしいですね。
長期的な視点での計画策定を期待します。
輪島市は、早期復旧・復興を目指し、様々な計画を策定し、市民参加の場を設けています。
2025年6月9日には「輪島港復旧・復興プラン」が策定され、短期的な復旧方針と中長期的な復興プランが示されました。
2025年2月26日には「輪島市復興まちづくり計画」が策定され、復旧・復興の基本理念と施策が体系的にまとめられています。
建築家の隈研吾氏を復興まちづくり特別アドバイザーに委嘱し、専門的な視点を取り入れ、歴史、文化、伝統、景観を活かした魅力的なまちづくりを推進しています。
計画策定にあたっては、復興まちづくり計画検討委員会が設置され、市民の意見を反映するため、住民懇談会や「わじま未来トーク」といった対話の場、住民アンケートが実施されました。
2024年12月25日から2025年1月23日には、輪島市復興まちづくり計画(案)に関するパブリックコメントが実施され、市民からの意見が募られました。
これらの取り組みを通じて、輪島市は住民との連携を深めながら、持続可能な復興を目指しています。
計画を立てるだけじゃダメだよね。ちゃんと市民の声を聞いて、みんなが納得するような復興プランを作らんと。まあ、焦らずじっくりと話し合ってほしいもんだね。
次のページを読む ⇒
奥能登豪雨の被災家屋解体支援、輪島市で実施。申請は終了も、長期避難者向け相談受付中。JPFは生活復興を支援。被災状況写真や義援金情報も。

