新潮社の校閲講座、5周年記念!対面とオンラインで校閲スキルを磨こう?5周年を迎えた新潮社の校閲講座、実践的な学びでスキルアップ!
校閲の世界へ飛び込もう! 新潮社が校閲講座5周年を記念し、対面・オンラインで開催。現役校閲者が教える実践的な内容で、校閲の基本から応用までを習得。AI時代の校閲の役割を考えるイベントも。プロの技を学び、言葉の未来を切り拓こう! 校閲スキルを磨き、出版業界で活躍したいあなたに。
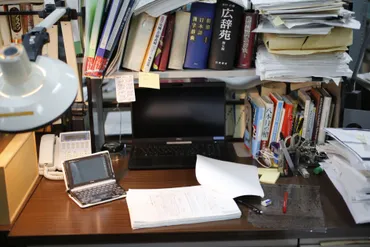
💡 新潮社が校閲講座5周年を記念し、対面とオンラインで講座を開催すること。
💡 校閲のプロである新潮社校閲部の現役校閲者が講師を務め、実践的な問題を通して校閲のポイントを学べること。
💡 毎日新聞校閲センターのイベント「ことば茶話」で、AIと校閲の未来について議論されること。
それでは、まずこの記事でご紹介する内容を3つのポイントにまとめました。
新潮社校閲講座:5周年記念、対面とオンラインで開講
新潮社の校閲講座、今年はどんな展開?
対面&オンライン開催!
新潮社の校閲講座が5周年!特別講座では、ベテラン校閲者による貴重な話が聞けます。
新聞、雑誌、文芸と、メディアごとの校閲の違いも学べそうですね。
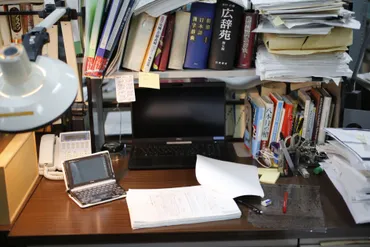
✅ 新潮社の校閲講座が2022年上旬に「新潮社の校閲講座〈特別編〉」として2つの特別講座を開講します。
✅ 2月4日は、新潮社のベテラン校閲者による「井上孝夫×飯島秀一 歴代校閲部長が語る「校閲という仕事」」が開催され、昭和・平成・令和と時代を超えた校閲の秘話を聞くことができます。
✅ 3月29日は、朝日新聞社と講談社の現役校閲者をゲストに迎えた「新聞×雑誌×文芸=校閲オンライントーク!」が開催され、それぞれのメディアにおける校閲の現場について、最新の話題や忘れられないエピソードなどを聞くことができます。
さらに読む ⇒|プレスリリース・ニュースリリース配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000434.000047877.html校閲のプロである新潮社校閲部の現役校閲者が講師を務める講座は、非常に魅力的ですね。
対面とオンライン、どちらも選べるのも良い点です。
実践的な問題を通して学べるというのも、スキルアップに繋がりそうです。
新潮社は、2016年から好評開催中の校閲講座を、今年5周年を迎え、対面講座とオンライン講座の両方を開催します。
対面講座は7月6日、9月7日、28日に神楽坂教室で、オンライン講座は8月31日と9月14日に開催されます。
各講座の内容は、新潮社校閲部の現役校閲者が講師を務め、「校閲とは何か」「どんな仕事か」をエピソードを交えながら解説し、実践問題を通して校閲のポイントを学ぶことができます。
対面講座は、校閲体験講座と校閲実践講座〈特別編〉、オンライン講座は「新潮社の校閲オンライン講座」の1種類が開催されます。
各講座の詳細や申し込み方法は、新潮社校閲講座のウェブサイトをご確認ください。
ふむ、校閲ってのは、出版物の品質を守る重要な仕事だな。5周年ですか。おめでとうございます!実践的な問題で学べるのは、即戦力になる人材育成には不可欠ですね。新潮社の講座、私も受けてみたいくらいだ。
新潮社の校閲オンライン講座(後編):実践的な問題を通して校閲を学ぶ
新潮社校閲オンライン講座(後編)で学べることは?
校閲の仕事内容と将来
校閲の仕事内容やポイントを解説するオンライン講座、いいですね。
iPad校閲の実演やAIに関する最新トピックも学べるなんて、時代に即した内容です。
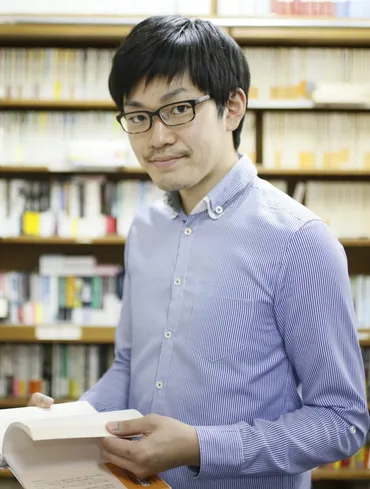
✅ 本講座は、新潮社の校閲部所属の講師が、校閲の仕事内容やポイントを解説するオンライン講座です。
✅ 講座では、実際の出版現場で用いられる校閲問題を事前に解いて準備し、動画内で解説を受けられます。
✅ さらに、iPad校閲の実演や「校閲とAI」など、最新のトピックも取り上げられており、校閲という仕事の現在地を理解することができます。
さらに読む ⇒新潮社本の学校出典/画像元: https://hon-gakko.com/lecture_page/%E6%96%B0%E6%BD%AE%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%A0%A1%E9%96%B2%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E8%AC%9B%E5%BA%A7%EF%BC%88%E5%89%8D%E7%B7%A8%EF%BC%89-%E6%A0%A1%E9%96%B2%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86/実践的な問題を通して校閲を学べるのは、非常に実践的で良いですね。
素読みの重要性からAIの限界、誤植のパターンまで、幅広い知識が学べるのは、すごく勉強になりそうです。
新潮社校閲部の甲谷允人氏による、約100分の講義動画「新潮社の校閲オンライン講座(後編)」が公開されます。
前編に引き続き、校閲という仕事の現在地と将来について、実践的な問題を通して解説します。
受講者は、事前に配布される問題を解いて準備し、動画内で解答・解説を確認することで、校閲のポイントを深く理解することができます。
講義内容は、素読みの重要性からAIや校正ソフトの限界、誤植のパターン、調べ物の深さ、新潮社のチェックマーク、デジタル時代におけるアナログ文化など、実際の校閲業務で直面する課題まで多岐にわたります。
さらに、優秀な校閲者の特徴、雑誌と書籍の校閲の違い、媒体やジャンルによる疑問点の差異、調べ物の技術など、幅広いテーマについても解説します。
受講者は、校閲問題の解答例から疑問の出し方や校正記号の使い方を学ぶことができ、実際の出版現場で役立つ知識を習得できます。
へえ〜、校閲にもAIが絡んでくる時代なんだね!でも、やっぱり人間がちゃんと見ないと、変なことになっちゃうこともあるんでしょ? 実践的な問題で学べるってのは、すごくいいね! 私も受けてみたいわぁ。
次のページを読む ⇒
AI時代、言葉の未来を語る!新潮社校閲部ベテラン甲谷氏が「ことば茶話」に登場。校閲の経験談、AIとの役割、Q&Aも。毎日ことばplus会員限定、見逃し配信あり。

