日野自動車と三菱ふそうトラック・バス経営統合は?EV、脱炭素化、競争激化への対応とは?日野と三菱ふそうの統合再始動:未来の商用車とCASE技術
日野自動車と三菱ふそうの統合は、国際競争激化と脱炭素化への対応が鍵。不正問題からの再出発、トヨタ・ダイムラーとの連携、そしていすゞとの差を埋めることが急務。世界販売減、赤字計上も、統合や新たな技術開発で巻き返しを図る。持続可能な社会を目指し、地域貢献や効率化も推進。商用車業界の未来を左右する、日野の挑戦から目が離せない!
統合協議の遅延と競合他社の動き
日野と三菱ふそうの統合、どうなる?
認証問題解決で再開
統合協議の遅延と競合他社の動きについて、見ていきましょう。
公開日:2025/04/22
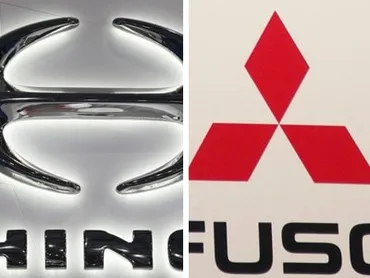
✅ 日野自動車と三菱ふそうトラック・バスが経営統合に向け最終合意に向けて調整に入りました。
✅ 統合はトヨタ自動車とダイムラーが持ち株会社を設立し、日野自動車と三菱ふそうトラック・バスがその子会社となる形で進められます。
✅ 統合により、日本の商用車業界は日野自動車・三菱ふそうグループと、いすゞ自動車とUDトラックスのグループの2陣営に集約されます。
さらに読む ⇒時事ドットコム:時事通信社が運営するニュースサイト出典/画像元: https://www.jiji.com/jc/article?k=2025042200778&g=eco日野自動車のエンジン認証不正問題による遅延が、今後の競争に影響を与えそうですね。
日野自動車と三菱ふそうトラック・バスの経営統合は、日野の米国でのエンジン認証不正問題により足踏み状態が続いていたが、日野が当局と和解し、統合に向けた協議が本格化する見通しとなった。
当初は2024年3月末までに最終契約を締結し、同年中の統合を目指していたが、認証問題対応や許認可取得などの影響で延期され、具体的な時期は未定となっている。
一方、いすゞ自動車は子会社化したUDトラックスとのシナジーを既に実現させ、共同開発車の投入や生産協業を進めるなど先行している。
日野は統合が遅れるほどいすゞとの差が開き、競争が激化する可能性もある。
ダイムラートラックも欧州市場で苦戦しており、トヨタグループとの協業による競争力強化が急務となっている。
4社はグローバルでの商用車競争激化を背景に、統合実現に向けて協議を加速させる必要があり、今後の進展に業界の注目が集まっている。
あら、大変ね。でも、頑張って!応援してるわ!
統合再始動と競争の加速
日野と三菱ふそうの統合が進むのはなぜ?
脱炭素化対応のため
統合再始動と競争の加速について、見ていきましょう。

✅ ダイムラートラック、三菱ふそうトラック・バス、日野自動車、トヨタ自動車の4社は、CASE技術開発の加速とMFTBCと日野の統合を目的とした基本合意書を締結しました。
✅ MFTBCと日野は対等な立場で統合し、商用車の開発、調達、生産分野で協業することで、グローバルな競争力のある日本の商用車メーカーを構築します。また、ダイムラートラックとトヨタは、統合会社の持株会社を同割合で保有し、水素をはじめCASE技術開発で協業することで、統合会社の競争力強化を目指します。
✅ 4社の協業は、日本の商用車の未来とモビリティ社会の未来を構築するための重要なパートナーシップであり、CASE技術強化によるカーボンニュートラル実現や、社会課題解決を通じて「商用車の未来を変えていくこと」を目指しています。
さらに読む ⇒総合出典/画像元: https://motor-fan.jp/mf/article/142350/日野と三菱ふそうの統合は、CASE技術開発の加速とカーボンニュートラル実現を目指していますね。
日野自動車は、米当局との和解によりエンジン認証不正問題がほぼ終結し、三菱ふそうトラック・バスとの経営統合協議が再び動き出す見通しとなりました。
これは、脱炭素化への対応が自動車業界で急務となっているため、両社が連携し、CASE対応や投資負担軽減による世界での競争力強化を目指しているからです。
世界では、脱炭素化に向けて、各社が協業を強化しています。
トヨタとBMWはFCシステムの共同開発、GMと現代自動車は車両やクリーンエネルギー技術での協業を検討しており、いすゞはホンダとFC大型トラックの開発で連携しています。
日野自動車と三菱ふそうの統合が遅れている間も、競合他社は次世代車の市場投入に向けてしのぎを削っています。
今後の競争力を左右するのは、商用車の脱炭素化対応の遅れを取り戻せるかどうかです。
素晴らしい!CASE技術の強化で、日本の商用車メーカーが世界を席巻する未来が見えるな!
日野自動車の業績と今後の取り組み
日野自動車は2026年3月期に世界販売台数をどれくらいに予想していますか?
11万5000台
日野自動車の業績と今後の取り組みについて、詳しく見ていきましょう。
公開日:2025/04/28

✅ 日野自動車と三菱ふそうトラック・バスの経営統合が、日野のエンジン認証不正問題の影響で遅れているが、日野自動車の小木曽社長は「統合に向けての課題をひとつクリアした」と述べ、統合を「1日でも早く」実現したい意向を示した。
✅ 統合の目的は、CASEの展開、特にカーボンニュートラルの技術開発を加速させるため。大型トラックはBEVでは対応できないため、Eフューエル、燃料電池、水素燃焼など、多様なパワートレインに対応する必要があり、個社単独では困難である。
✅ トヨタ自動車グループの日野とダイムラーグループの三菱ふそうは、それぞれの強みを生かし、小型車の電動化技術と大型車のエンジン技術を融合することで、開発部門・分野の重複を解消し、統合による相乗効果を期待している。
さらに読む ⇒レスポンス()出典/画像元: https://response.jp/article/2025/04/25/394964.html日野自動車は、経営統合と脱炭素化への対応を両立させ、今後の成長を目指していることが分かりますね。
日野自動車の業績ハイライト(連結)は、2016年から2023年までの販売台数、売上高・営業利益、当期純利益・ROE、設備投資・研究開発費、車両生産台数、輸出台数を示しています。
販売台数は、日本、アジア、北米、中南米、オセアニア、中近東、アフリカ、欧州の各地域において、2016年以降は概ね横ばい傾向ですが、2023年には減少しています。
売上高・営業利益、当期純利益・ROEは、2021年から「収益認識に関する会計基準」の適用により、数値が変更されています。
設備投資は、2020年度から増加傾向にあります。
研究開発費は、2021年度から増加傾向にあります。
車両生産台数(日本+海外)は、2016年以降は概ね横ばい傾向にあります。
輸出台数は、2016年以降は概ね横ばい傾向にあります。
日野自動車は、持続可能な地域交通の実現を目指した自家用有償トータルサポート、神奈川県葉山町との連携によるごみ収集支援サービス「GOMIRUTO」、統合報告書の発行、カーボンニュートラルに向けた取り組みなど、新たな領域への取り組みを進めています。
日野自動車の小木曽聡社長は、三菱ふそうトラック・バスとの経営統合協議が米当局との和解合意により前進し、最終契約に向けた協議が続いていることを明らかにしました。
世界で中国勢の台頭を背景に、脱炭素化への対応としてEVやFCVなどの新たな技術開発を個社で進めることが困難となる中で、経営統合による協業で時間と投資の負担を軽減する方針です。
日野自動車は、2026年3月期の世界販売台数見通しを前期比8.0%減の11万5000台と発表しました。
インドネシア市場の低迷が影響しており、中国勢の台頭による競争激化が懸念されています。
経営統合は、インドネシア市場でのシェア維持・向上に大きな意味を持つと考えられます。
25年3月期の決算では、米当局への制裁金を含む認証関連損失により2177億円の赤字となりましたが、26年3月期は200億円の黒字転換を見込んでいます。
小木曽社長は、世界経済の先行きは不透明であることを強調し、生き残るためのさまざまな対策を講じる意向を示しました。
日野自動車は、持続可能な地域交通の実現に向けた取り組みとして、自家用有償トータルサポートサービスを提供しています。
このサービスは、運行管理受託サービスを通じて、働き方の改善や交通空白地の解消を目指しています。
また、神奈川県葉山町では、ごみ収集支援サービス「GOMIRUTO」を2024年4月から提供開始し、車両の位置情報をリアルタイムで把握する動態管理システムを活用して業務の効率化を図っています。
さらに、日野自動車は初となる統合報告書を発行し、会社の新生と信頼回復に向けた「3つの改革」の進捗やサステナビリティに関する取り組みについて掲載しています。
同社はカーボンニュートラルに向けた取り組みについても積極的に進めており、今後も持続可能な社会の実現に貢献していくことを目指しています。
へぇー、色々やってるんだね!ま、頑張りなさいよ!
本日の記事では、日野自動車と三菱ふそうトラック・バスの経営統合について、様々な角度から解説しました。
今後の動向に注目ですね。
💡 日野自動車と三菱ふそうトラック・バスの経営統合は、脱炭素化と国際競争を勝ち抜くための重要な戦略。
💡 経営統合の遅れを取り戻し、EV/FCV等の技術開発を加速させることが今後の課題。
💡 日野の業績回復と、新たな取り組みへの挑戦にも注目が集まる。


