ゴーン氏、日産経営陣を痛烈批判! 日本の司法制度にも疑問符?日産の現状とゴーン氏の主張、日本の司法制度への批判
ゴーン氏が語る日産の現状と未来!経営統合破談の真相、日本の司法制度批判、そしてEV戦略の正しさ。自動車業界再編の過去と未来を紐解く、衝撃のインタビュー!
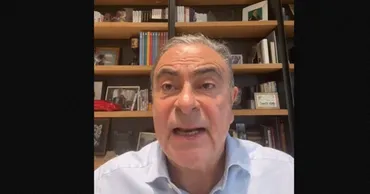
💡 カルロス・ゴーン氏が、日産経営陣の無能さを痛烈に批判
💡 ゴーン氏、日本の司法制度を「人質司法」と批判
💡 日産とホンダの経営統合交渉が破談
それでは、ゴーン氏と日産の現状について詳しく見ていきましょう。
ゴーン氏、日産経営陣を痛烈批判、日本の司法制度にも疑問符
ゴーン氏、日産の現状をどう見ていますか?
1999年以前レベルに後退
ゴーン氏の主張は非常に興味深いですね。
公開日:2024/12/28
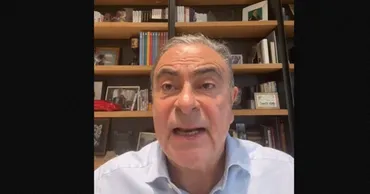
✅ カルロス・ゴーン元日産会長は、週刊エコノミストのインタビューで、日産の現状について、経営陣の無能さ、ビジョンと知識の欠如を批判し、HVよりもEVに注力すべきだったと主張しました。
✅ また、日産がホンダやホンハイとの統合協議を進めている状況に対して、日産は最終的にこれらの企業の意思に従わざるを得ない状況になると懸念を示しました。
✅ さらに、ゴーン氏は自身の経験に基づき、日本の「人質司法」について批判し、これは民主主義国家として信じられないことであり、日本の国際的な評価を下げていると主張しました。
さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/premier/business/articles/20241227/biz/00m/020/004000cゴーン氏の言葉は、日本の司法制度に対する大きな問題提起と言えますね。
カルロス・ゴーン氏は、週刊エコノミストの単独インタビューで、日産の現状は1999年以前のレベルまで後退したと主張しています。
ゴーン氏は、日産の経営陣にビジョンも業務効率に関する知識も欠如していると批判しました。
さらに、日産がホンダやホンハイとの統合協議を進めていることについて、いずれも日産が支配される立場になると指摘しました。
特にホンダとの統合では、エンジニアリング主導のホンダが主導権を握り、日産は二流の会社になるとの見解を示しました。
ゴーン氏は、日本の司法制度を「人質司法」と批判し、袴田巌さんの事件を例に挙げて、日本の司法制度の未発達さを指摘しました。
ゴーン氏は、日産の経営危機の原因は、ハイブリッド車の技術力不足ではなく、EV技術という強みを活かさずに古い経営体質に戻ったことにあると主張しています。
ゴーン氏は、EVへの投資は正しい判断だったとし、今日の業界の勝者はEVに投資した人々だと語っています。
さすがゴーンさん! 経営者としての鋭い分析力と、日本の司法制度に対する批判には、耳を傾けざるを得ないですね。
自動車メーカー統合の歴史:成功と失敗の教訓
自動車業界で統合・合併は成功するのか?
成功例と失敗例あり
自動車メーカーの統合の歴史は、成功と失敗の両面がありますね。
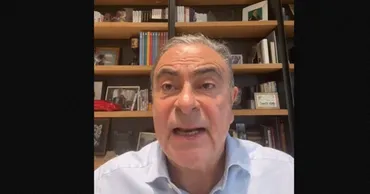
✅ ホンダと日産自動車が経営統合に向けた協議を開始し、2026年8月上場予定の持ち株会社を設立することで合意しました。新会社はホンダが主導し、日産は完全子会社となります。
✅ 統合により、世界販売台数でトヨタ自動車、フォルクスワーゲンに次ぐ3位となり、国内ではトヨタ陣営とホンダ陣営の二極化が強まることが予想されます。
✅ 背景には、EV開発競争でテスラやBYDに先行を許している現状への危機感があり、統合によってスケールメリットを生み出し、売上高30兆円、営業利益3兆円超の自動車メーカーを目指しています。
さらに読む ⇒時事通信ニュース出典/画像元: https://sp.m.jiji.com/article/show/3413752?free=1ホンダと日産の統合は、日本の自動車業界に大きな影響を与える可能性がありましたね。
日産とホンダの経営統合が破談となったことを受け、自動車メーカーの統合や合併の歴史、成功・失敗パターンを振り返ります。
1960年代には日産がプリンス自動車を吸収合併、トヨタはダイハツの子会社化を進めました。
1990年代にはマツダがフォードの傘下入り、日産と三菱はルノーとアライアンスを結びました。
2000年前後は「400万台クラブ」という言葉が流行し、多くの自動車メーカーが統合や合併を行いました。
しかし、リーマンショック後にはGMやフォードが揺らぎ、傘下にあったブランドが放出され、新たな提携が生まれました。
成功例としては、トヨタとダイハツの提携が挙げられます。
両社は役割分担を行い、安定して成長を続けています。
失敗例としては、プリンスのブランド消失、フォードによるマツダやボルボなどの放出などがあります。
日産とホンダの未来については、引き続き、経営統合以外のアライアンスや提携の可能性を探る必要があるでしょう。
なるほど、統合の歴史を振り返ると、成功するためには、企業文化や経営方針のすり合わせが重要なんだな。
次のページを読む ⇒
ホンダ日産統合、破談!文化・戦略の溝、日産独立志向が壁に。今後の競争は激化か?

