能登半島地震支援:義援金と地表変状調査の現状と課題?能登半島地震における義援金と地表変状の記録
能登半島地震の義援金受付、359億円超が集まる。被災者の生活再建を支えるため、石川県と日本赤十字社などが連携。地表変状の緊急調査も実施。義援金と支援金の違いを理解し、信頼できる寄付先を選び、被災地を応援しましょう。
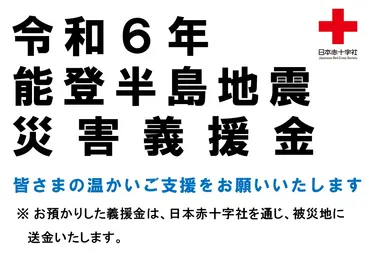
💡 令和6年能登半島地震の被災地支援のため、義援金募集が開始。様々な団体が窓口となり、多様な寄付方法が提供されています。
💡 地震による地表変状の調査が行われ、地表地震断層の存在が確認されました。今後の防災に役立てられます。
💡 義援金と支援金の違いを理解し、目的に合った寄付を選ぶことが重要です。詐欺に注意し、確かな情報に基づいて行動しましょう。
今回の記事では、能登半島地震における義援金と地表変状の調査について掘り下げていきます。
まずは、義援金募集の詳細について見ていきましょう。
揺れる大地と、立ち上がる人々の想い
能登半島地震の義援金、何億円集まった?
359億円以上 (3月17日時点)
厚木市では、能登半島地震の被災者支援のため、義援金募集を行いました。
公共施設やイベントでの募金活動に加え、街頭募金も実施されました。
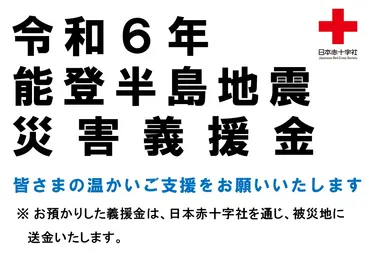
✅ 厚木市は、令和6年能登半島地震災害義援金として、公共施設やイベントで募金箱を設置し、街頭募金も実施しました。
✅ 集まった義援金は日本赤十字社を通じて被災地に送金され、寄付金控除の対象となります。振込での寄付も可能で、受領証の発行も受け付けています。
✅ 寄付は「被災地全域」と「地域限定」の2種類があり、それぞれ日本赤十字社の口座と石川県支部の口座が設けられています。受領証の発行方法や振込手数料に関する注意事項が記載されています。
さらに読む ⇒ホーム厚木市出典/画像元: https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/sdgs/about/40108.html厚木市の義援金募集活動は素晴らしいですね。
集まった義援金は被災地に送られ、寄付金控除の対象となるそうです。
振込での寄付も可能で、受領証の発行も行われているとのことです。
2024年1月、能登半島を襲った大地震は、甚大な被害をもたらしました。
この災害に対し、石川県は日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会と連携し、被災者支援のための義援金受付を開始しました。
受付期間は2024年1月4日から2025年12月26日までと定められ、専用口座(北國銀行とゆうちょ銀行)が用意されました。
3月17日時点で359億円を超える義援金が集まり、被災者の生活再建を支えるために活用されます。
素晴らしい取り組みだな! こういう時こそ、みんなで助け合わなきゃな。寄付は、社会貢献にもなるし、節税にもなるから、俺も積極的に参加しよっと!
地殻変動の記録:断層の痕跡
珠洲市の地表変状、何が原因?地震断層?
はい、地震によって形成された地表地震断層。
東京大学の研究者らが、能登半島地震による地表変状を調査しました。
その結果、地表地震断層の存在が明らかになりました。
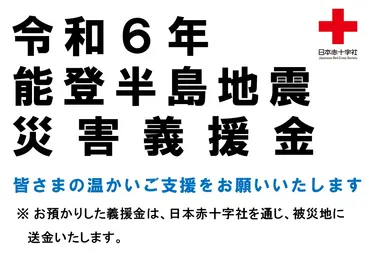
✅ 東京大学の研究者とともに、安江准教授と立石准教授が能登半島地震による地表変状を石川県珠洲市若山町で調査しました。
✅ 調査の結果、若山川沿い約2kmにわたり、最大上下変位量2m、左横ずれ変位量1.2mを示す地表変状が確認されました。
✅ これらの変状は地すべりとは無関係で、令和6年能登半島地震の際に形成された地表地震断層と推定されています。
さらに読む ⇒富山大学都市デザイン学部出典/画像元: https://www.sus.u-toyama.ac.jp/2024/news/surface-ruptures/地表変状の調査は、地震のメカニズムを理解し、今後の防災対策に役立てるために非常に重要です。
詳細な調査結果を待ちたいですね。
地震発生後、東京大学の研究者らと安江准教授、立石准教授は、石川県珠洲市若山町で地表変状の緊急調査を実施しました。
その結果、若山川沿い約2kmにわたり、最大2mの上下変位と1.2mの左横ずれ変位が確認されました。
特に珠洲市若山町では、若山川に沿って約4kmの範囲で隆起帯が認められ、水田や道路の切断、最大195cmの落差、傾動による変形が観察されました。
これらの変状は、地震前の空中写真にはなく、地すべりとも異なることから、地震によって形成された地表地震断層と推定されています。
へぇ~、地表地震断層か。専門的なことは分からんけど、自然の力ってすごいな。調査結果を参考に、もっと安全な街づくりを目指してほしいもんだね。
次のページを読む ⇒
被災者支援は義援金と支援金、2つの形があります。使途を確認し、目的に合った寄付を!能登半島地震の復興を支えましょう。

