岩手県大船渡市の山林火災、鎮圧までの記録と復興への道(山林火災、消防隊、避難指示)?大船渡市山林火災、鎮圧と避難指示解除、復興への第一歩
岩手県大船渡市を中心に発生した大規模山林火災。延焼面積2900ha、住宅102棟が被害に。全国から集まった消防隊員2000人超による消火活動は困難を極め、90歳男性が犠牲に。鎮火に向けた懸命な努力と、被災者の復興への願いを描く。

💡 2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模な山林火災。焼失面積は2900ヘクタールに。
💡 全国から集まった消防隊員2020人による消火活動と困難さ。鎮火まで約2週間。
💡 鎮圧宣言、避難指示解除。被災者の復興への道のり。住民の決意。
それでは、今回の山林火災で明らかになった多くの事実を、時系列に沿って見ていきましょう。
相次ぐ山林火災の発生
大船渡市、陸前高田市で相次いだ山林火災、原因は?
飛び火の可能性は低いが、火種や地形も原因か。
まず、最初の火災発生から鎮圧までの状況を見てみましょう。

✅ 2月26日に岩手県大船渡市で発生した山林火災は延焼が続いており、焼失面積は600ヘクタールを超え、住宅84棟に被害が出ています。
✅ 消火活動は夜を徹して行われ、自衛隊のヘリコプターによる空中消火も行われています。
✅ 大船渡市三陸町綾里地区と赤崎町合足地域の住民873世帯2114人への避難指示が継続中です。
さらに読む ⇒出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/ibc/1755173?display=1火災の規模が非常に大きく、広範囲にわたって被害が出たことがわかります。
人的被害が出たことも大変痛ましいです。
2月19日、岩手県大船渡市綾里地区で山林火災が発生しました。
その後、25日に鎮圧されましたが、同日、綾里地区から約9km離れた陸前高田市にまたがる山林火災が発生し、26日に鎮圧されました。
さらに26日には、1件目から2km、2件目から7kmほどの距離にある大船渡市で新たな火災が発生し、大規模な延焼が続きました。
日本防火技術者協会の鈴木弘昭理事は、これらの火災の関連性を明確には断定できないものの、距離が離れていることから飛び火の可能性は低いとしながらも、地形や熱気流、火種の可能性を指摘しています。
被害は合足漁港と綾里漁港の間の集落に集中し、住宅84棟以上が焼失、男性1人の焼死体も発見されました。
いやー、それにしても、焼失面積が広範囲にわたっているな。これは、保険会社は大忙しだな!
困難を極めた消火活動
山林火災、消火活動なぜこんなに難しい?
熱気流、風向き、夜間など厳しい状況。
次に、消火活動の困難さについて見ていきましょう。
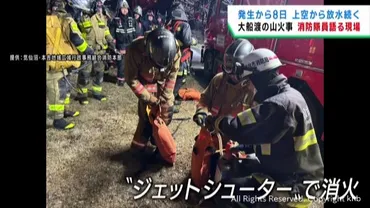
✅ 岩手県大船渡市の山火事に対し、宮城県南三陸町の消防隊員が緊急消防援助隊として派遣され、消火活動にあたった。
✅ 炎は隊員の目の前まで迫り、斜面での活動は疲労が大きく、ホースの展開も困難な状況の中、安全管理に注意しながら消火活動を行った。
✅ 表面を消しても土中に火種が残っているため、消火が困難な状況が続いており、消防隊員は市民の不安を取り除くため、引き続き消火活動を行う。
さらに読む ⇒東日本放送出典/画像元: https://www.khb-tv.co.jp/news/15657580消火活動がいかに困難を極めたかがよくわかりますね。
消防隊員の皆様の献身的な活動には頭が下がります。
消火活動は難航し、ヘリコプターからの放水が熱気流の影響で効果が薄れるなど、大規模な山林火災の消火の困難さが浮き彫りになりました。
乾燥した気候が続いていましたが、人為的な火災発生の可能性は低いとされていました。
全国から集まった約1700人の消防隊員が消火活動にあたり、夜間の消火活動の困難さや風向きの変化、煙に囲まれる危険、地表面の高温など、厳しい状況下での活動が続きました。
宮城県内の消防隊員も応援に駆けつけ、水の確保の難しさや消しても再燃する火との戦いなど、困難を極めました。
あらまぁ、ヘリからの放水も効果が薄かったって? 自然相手は本当に手強いわね。でも、消防隊員の皆さんの頑張り、本当にすごい。
次のページを読む ⇒
大船渡市を襲った大規模火災。消防隊2020人が集結し鎮火へ。甚大な被害の中、復興への道を探る。消防隊員の献身的な活動を記録。

